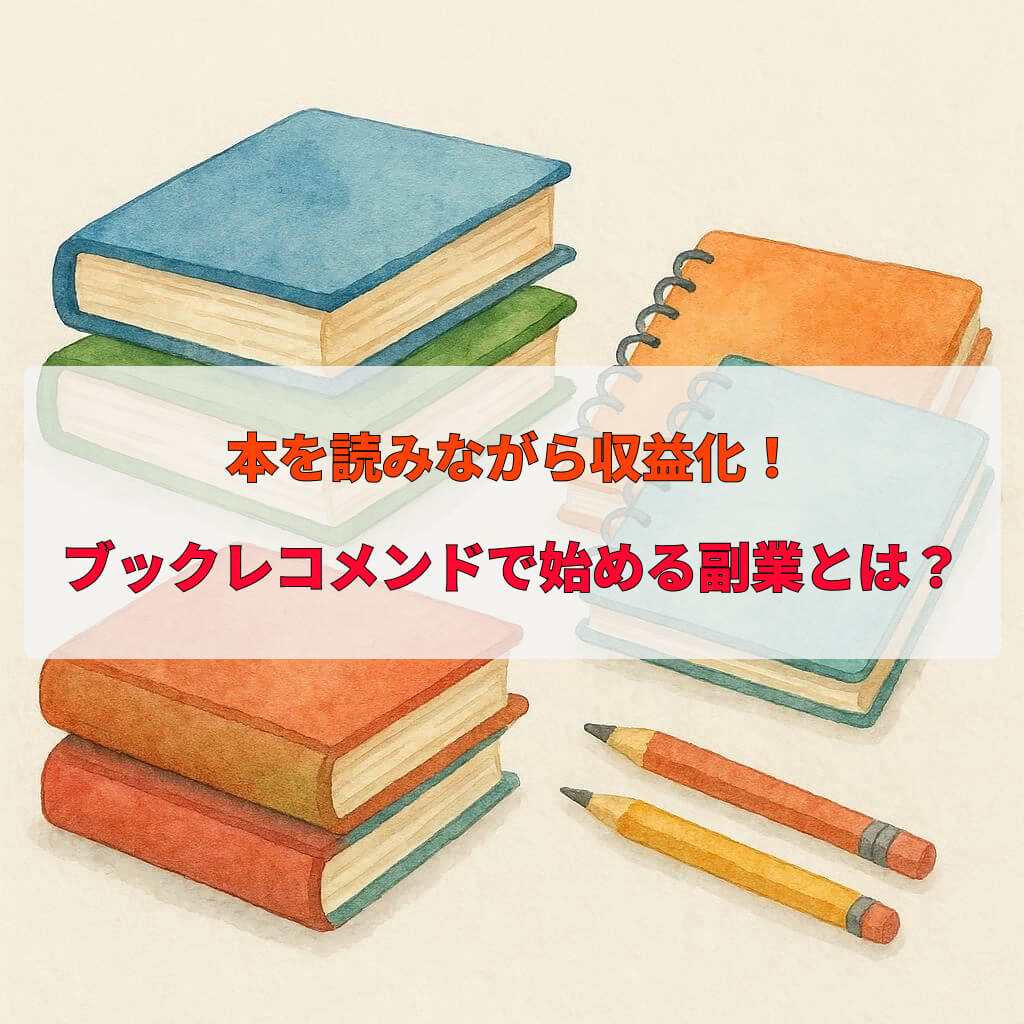ここ数年で副業という言葉を耳にする機会がぐっと増えましたよね。
背景には、以前よりも自由に働き方を選べる時代になったことがありますが、
いざ副業を始めようとすると、「自分には何ができるのだろう」「スキルや時間が足りなくて難しそう」と感じる人も少なくありません。
そんな中、本を読むことが好きな人にオススメしたい副業として、書籍紹介あります。
この記事では、書籍紹介を活用した副業の仕組みと、実際の始め方をわかりやすくご紹介します。
この記事で分かること
- 副業のトレンドと働き方の多様化
- 書籍紹介副業の魅力や活用のポイント
- 書籍紹介副業の始め方

記事の最後では、実体験をもとに書籍紹介副業の具体的なステップもご紹介していますよ。
副業って、何かいいのないの?
実は、自宅の空きスペースを貸すだけで
\収入につながる方法があります👇/
副業にも多様な働き方の選択肢が増えた?
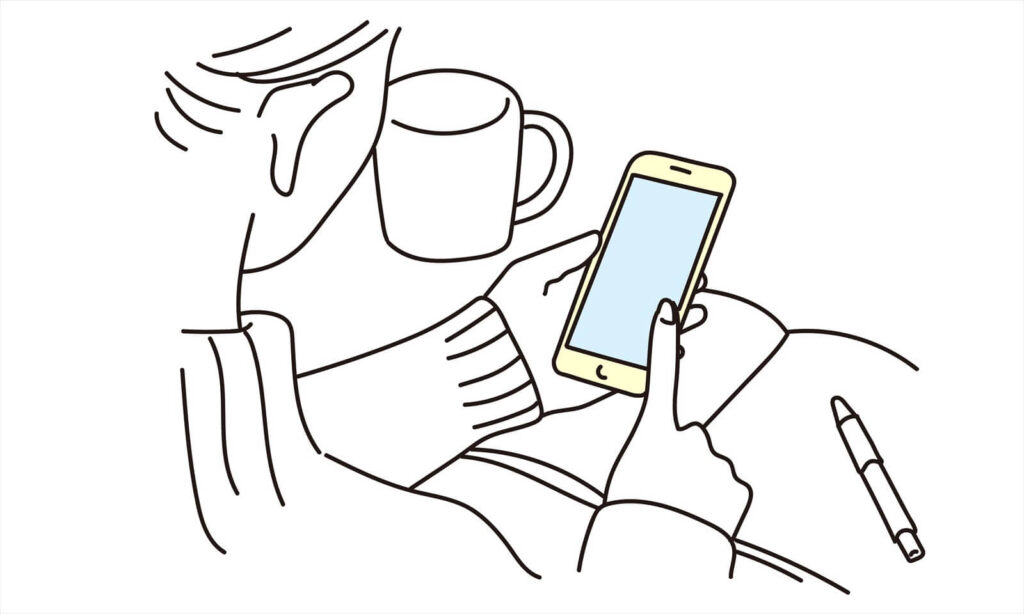
現代の副業では、Web制作やライティング、翻訳、動画編集など、場所に縛られずにできる仕事が主流になりつつあります。
これにより、自宅やカフェなど好きな場所で働きながら収入を得られ、本業との両立もしやすくなるなど、ライフバランスの向上にもつながっています。

まずは、2025年の副業の特徴や種類について見ていきましょう。
将来のために、収入源をひとつ増やしたい方へ
今ある資産を活かして始められる副業
\空きスペースを収入源に👇/
今ある資産を活かせる副業👇
駐車場の貸出に関して詳しくはこちら
身近になってきた副業の話
ここ数年で、副業はぐっと身近な存在になってきました。
では、なぜこのような働き方が広がってきたのでしょうか。
主な理由は、大きく分けて以下の3つです。
1. 働き方の自由度が高まったこと
2. 収入やキャリアの多様化を求める人が増えていること
3. ITやデジタルツールが進化したこと
リモートワークやフレックスタイム制度の普及により働き方の自由度が高まり、空き時間を活用して副業に取り組みやすい環境が整ってきました。
また、人生100年時代を見据え、給与だけに頼らず収入源を増やしたいというニーズが広がる中、ITやデジタルツールの進化によって、自宅やカフェなど場所を選ばずに仕事ができる環境が整ったことも、大きな要因の一つです。
| 年 | 副業者数(万人) |
|---|---|
| 2002 | 236.4 |
| 2007 | 241.5 |
| 2012 | 214.6 |
| 2017 | 245.1 |
| 2022 | 304.9 |
出典:総務省『図2 副業がある者の数(非農林業従事者)及び追加就業希望者数(非農林業従事者)の
推移(2002年~2022年)-全国』より
副業にはどんな種類があるの?2025年版
2025年現在の副業事情は、テクノロジーの進化や働き方改革の浸透により、以前よりも多様化・柔軟化しています。

あくまで、どういったことが副業としてできるのか、以下を参考にしてみてくださいね!
2025年現在の副業の主な種類
1. オンライン系スキル
・プログラミング・Web開発
・デザイン・動画編集
・ライティング・翻訳
・Webマーケティング
2. クリエイティブ系
・ハンドメイド販売
・写真・イラスト販売
3. シェアリング・サービス型
・配達・運転代行
・民泊・レンタルスペース
・家事・ペットシッター
4. 投資・資産運用系
・株式・FX・暗号資産投資
・不動産投資型副業
・ポイント・キャッシュバック活用
5. 教育・コンサル系
・オンライン講座・家庭教師
・コーチング・コンサル
6. 趣味・特技を活かす系
・ゲーム・配信
・ブログ・SNS運営
・趣味の販売
副業のスキルはどうやって身につけるの?
副業に必要なスキルは、短期間で身につけられるものもあれば、経験や継続学習が必要なものもあります。
例えば、WebライティングやSNS運用は比較的短期間で習得可能ですが、プログラミングやマーケティング戦略の立案は実務経験を通じて学ぶ必要があります。

副業のスキルの身につけ方には、以下6つの方法がありますよ。
副業のスキルの身につけ方
1. オンライン講座・学習プラットフォーム
・プログラミングやデザイン:Udemy、Schoo、Skillshareなどで体系的に学ぶ。
・マーケティングやライティング:Webマーケティングスクール、コピーライティング講座受講。
・語学・翻訳:オンライン英会話や翻訳トレーニング。
2. 書籍・教材で独学
・実務に役立つ専門書や最新の参考書で学習。
・基礎を理解した後、演習や模擬案件で実践力を高める。
3. 実務経験を通じて習得
・小さな案件から副業をスタートして、経験を積みながらスキル向上。
・クラウドソーシング(ランサーズ、クラウドワークス、Upworkなど)で実務案件を受注。
4. コミュニティ・勉強会に参加
・オンラインサロンやSNSコミュニティに参加。
5. 模擬プロジェクトやポートフォリオ作成
・自身で作品やサービスを作成してみる。
・作成したものをポートフォリオとして公開し、スキルの証明に活用。
6. 資格取得や検定
・副業に関連する資格を取得することで信頼性アップ。
例:FP技能士(金融系副業)、ウェブ解析士(マーケティング系)、TOEICや翻訳検定(語学系)など。
注目のマイナー資格について
\詳しくはこちら👇/
マイナー資格に関する関連記事
・マイナーだけどすごい資格|2026年度版の注目&おすすめ資格まとめ
書籍紹介で稼ぐ副業とは?
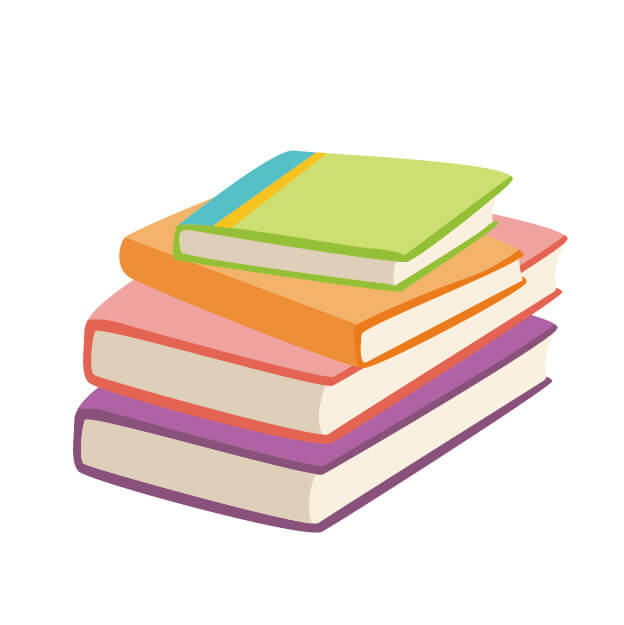
副業にはさまざまなジャンルがあることは、第一章でお伝えした通りです。
では、書籍紹介を活用した副業の方法をご存知でしょうか。
ウェブライティングやホームページ制作などは特別なスキルが必要ですが、
書籍紹介を活用した副業であれば、比較的手軽に始めることができます。

この章では、書籍紹介を活用した副業のメリットやデメリットについて整理していきます。
関連記事
・副業スタート前の確認ポイント|就業規則と自身に適した副業の選び方
読書と収入がつながる新しい仕組み
書籍紹介とは、その名の通り、自身が読んだ本を感想文やレビューとして発信し、収入につなげる新しい副業の形です。
投稿しただけでは報酬は発生しませんが、ブログやSNSに感想記事を掲載し、記事内に設置した購入リンクやクリック報酬型リンク、レコメンド機能などを通じて、読者が行動した際に報酬を得ることができます。
この副業の魅力は、単に収入を得るためだけに本を紹介するのではなく、自身が本当に面白いと思った本や、読んでほしい本を読者に届けられる点にあります。

筆者自身も、副収入のひとつとして書籍紹介を活用していますよ。
参照記事
・「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか(三宅 香帆)の次に読む本は
書籍紹介とアフィリエイトプログラムの違い
書籍紹介は、一見すると一般的なブログやアフィリエイトプログラムに似ているように見えますが、いくつかの大きな違いがあります。

一般的なアフィリエイトとどの点が異なるのか、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
1. 紹介対象が限定されている
書籍紹介の副業は「本」という明確なジャンルに特化しているため、コンテンツの方向性が定まりやすく、読者に専門性や信頼性を示しやすいのが特徴です。
一方、ブログやアフィリエイトでは、食品や家電、サービスなど幅広い商品を扱うことができますが、読者層に合わせた適切なマーケティングが求められます。
2. コンテンツ作りが比較的シンプル
書籍紹介の場合は、自身が読んだ内容や感想、どのような人に向いているかといった情報を整理するだけでコンテンツを作成できるため、商品の説明やスペックを調べる必要はほとんどありません。
一方、一般的なアフィリエイトでは、商品リサーチやSEO対策、競合分析などの作業が必要になることが多く、初心者にとってはハードルが高くなります。
3. 読者との信頼関係が作りやすい
書籍紹介は、自身の体験や感想をもとに発信できるため、文章に個性が出やすく、読者との信頼関係を築きやすいというメリットがあります。
これに対して、食品や家電などの一般商品を紹介する場合は、実際に使用したレビューでなければ信頼性が低くなりがちです。
課題本を選んでレビューする流れ
では、どのように書籍紹介を活用した副業を行うのでしょうか。
書籍紹介を活用した副業のステップは、主に以下の6つです。
①ジャンルやテーマを決める
自分の得意分野や興味のあるジャンルを軸にすることで、記事の方向性を定めやすくなります。
②紹介する本(課題本)を選ぶ
話題の本やベストセラー、自身が実際に読んで面白いと思った本を選ぶと、レビューの説得力が高まります。
③読書しながらポイントを整理する
内容、印象に残った箇所、学びや気づき、どのような人に向いているかなどをメモしておくとレビュー作成がスムーズです。
④レビュー記事の構成を考える
寄稿にあたって、記事構成を次の6つのステップで整理します。
1. 基本の流れ
2. 本の概要(タイトル・著者・ジャンル)
3. 自分の感想や印象
4. 本から得た学びや気づき
5. 読者へのおすすめポイント
6. 購入リンクやレコメンドの設置 など
⑤記事を作成・公開する
読者にとって読みやすい文章にまとめ、ブログやSNSに公開します。
⑥反応を確認して改善する
クリック数や購入数、読者の反応を確認しながら、レビューの書き方や本の選定を改善します。

上記の6つのステップは、あくまで一般的な書籍紹介の進め方です。
次の章では、より具体的に副業として収益を得るためのポイントや実践方法について解説していきますよ!
ブックレコメンドで収益化するには?
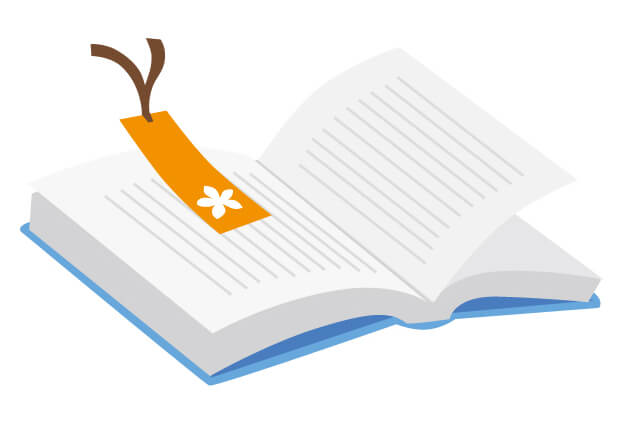
ブックレコメンドという書籍紹介サービスをご存知でしょうか。
ブックレコメンドは、単なる書評サイトではなく、読者に本をおすすめすることを目的に運営されているメディアです。

この章では、ブックレコメンドの活用の仕方をご紹介していきます。
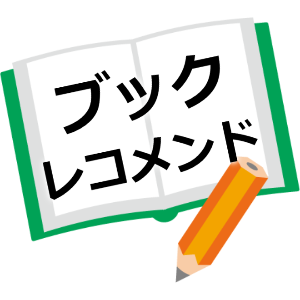
ブックレコメンドってどんなサービス?
ブックレコメンドは、単なる書評サイトではなく、読者におすすめの本を実際に手に取ってもらうことを目的に運営されているメディアです。
このサイトの特徴のひとつは、読者が本を読んだあとに、自身のおすすめ本を紹介できる点です。
寄稿者は本を二冊一組で紹介することで、テーマや内容のつながりを意識しながら、読者が自然に次の一冊に興味を持てるよう工夫します。
その結果、ただ読むだけでなく、「自分に合った本を見つける楽しみ」や「次に読む本のヒント」を得られるのが、このサイトの大きな魅力です。

ブックレコメンドの3つの活用の仕方
ブックレコメンドの活用の仕方には、大きく分けて以下3つの方法があります。
ブックレコメンドの3つの活用法
①レコメンド記事から読みたい本を見つける
・他の寄稿者が紹介する本の中から、自身の興味に合った一冊を見つけることができます。
②書評を寄稿して収益を得る
・自身の読書体験や感想を記事として投稿することで、収益を得ることができます。
③自身の本(執筆本など)を広告する
・自身が執筆した書籍や関連本を紹介し、多くの読者に知ってもらうことができます。

つまり、お気に入りの本を見つけたり、収益に活かしたりすることもできるということですよ。
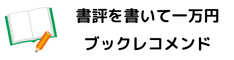
寄稿して収益を得る5つのステップ
先ほどの章で「書評を寄稿して収益を得る」と述べましたが、
読んだ本の内容を寄稿することで、副業として収入を得ることもできる、ということです。

ブックレコメンドに寄稿して、収益を得るまでのステップは、主に次の5つです。
寄稿して収益を得る5つのステップ
①ブックレコメンドサイトの「書評を書きたい方へ」をクリック
・書評寄稿に関する情報ページに移動します。
②「寄稿者募集フォームを表示する」をクリック
・寄稿者登録や応募ページに進みます。
③読書ライター応募フォームに必要事項を記入
・名前や自身のブログURLなどを入力します。
④書評を執筆・投稿
・課題本の感想と、自身がオススメする本の詳細を記入して投稿します。
⑤クリックなどの成果に応じて報酬を受け取る
・記事の閲覧や書籍購入などに応じて収益が発生します。

筆者が寄稿してみた結果については、以下に記載していますので、ご参考ください。
参照サイト👇
・「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか(三宅 香帆)の次に読む本は
まとめ
今回の記事のまとめです。
副業にはさまざまなジャンルがありますが、特に読書好きの方には、書籍紹介を活用した副業がおすすめです。
寄稿することで収益を得られるだけでなく、自分の書いた本や関連商品を広告として活用できる点も魅力です。