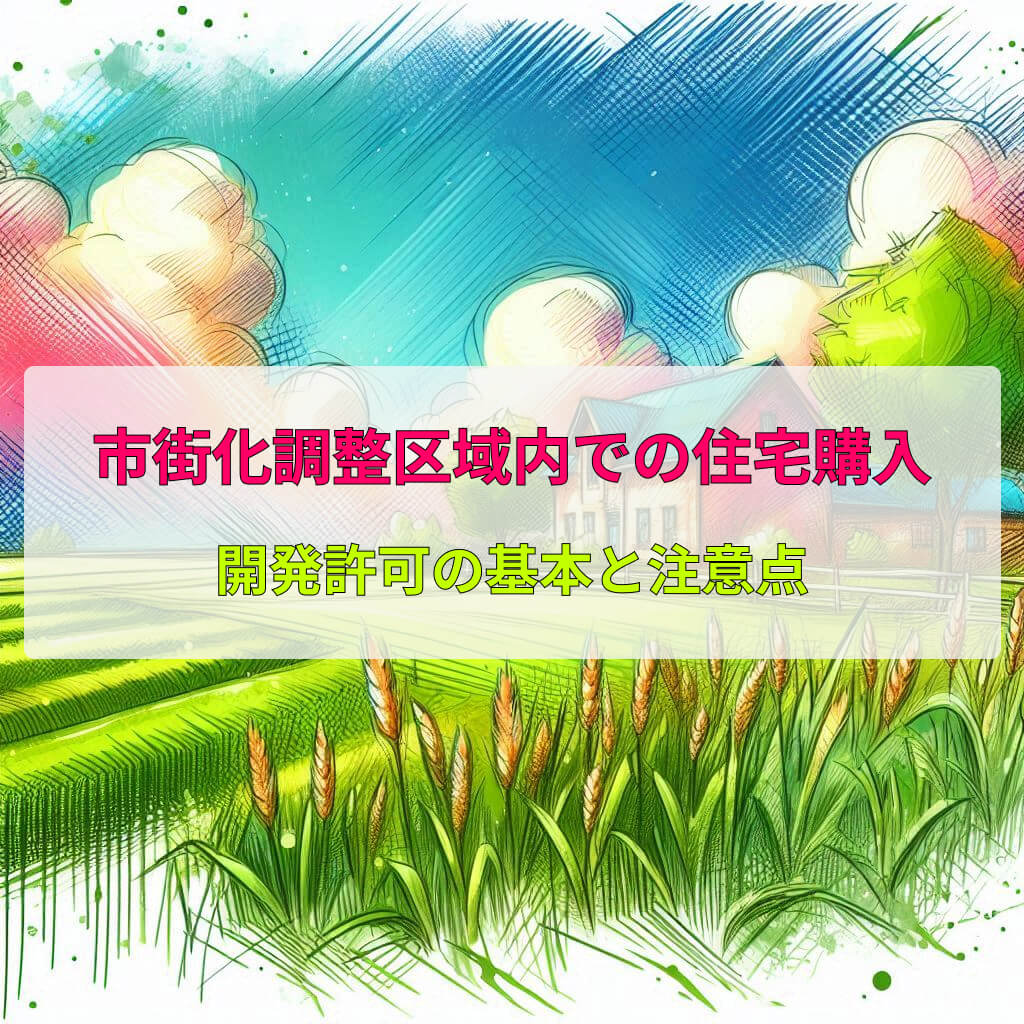『市街化調整区域内では、家を建てられないの?』
市街化調整区域は、都市計画法に基づき、住宅や商業施設の建設が制限される地域です。
そのため、市街化調整区域に指定された土地では、建物の建設が難しく、制限をクリアするためには都道府県知事の許可が必要になることがあります。
本記事では、市街化調整区域の基本的な特徴をはじめ、建築制限の内容や土地購入前に知っておくべきポイントを詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 市街化調整区域の基本的な特徴とは?
- 市街化調整区域内での建築制限について
- 土地や建物を購入する前に知っておきたいポイント

市街化調整区域で戸建てを建てたい場合など、その建築制限について学んでいきましょう。
市街化調整区域とは?基本的な概要と特徴
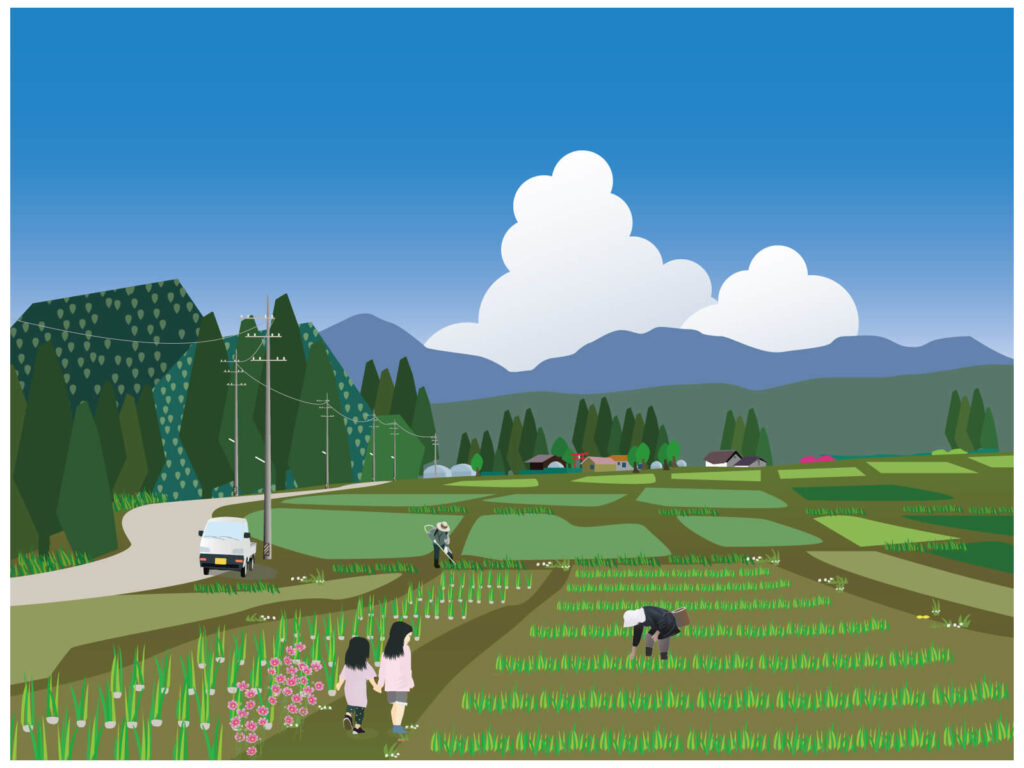
そもそも、市街化調整区域とはどのような地域なのでしょうか。
冒頭でも触れたように、市街化調整区域は都市計画法に基づき、住宅や商業施設の建設を制限するエリアのことを指します。

まずは、都市計画法について触れながら、市街化調整区域の概要を見ていきましょう。
市街化調整区域の特徴
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて指定され、開発や整備を制限する区域で、主に農地や自然環境を保護する役割を担っています。
この区域は「市街化を抑制すべき区域」と位置づけられており、原則として新たな建物を建てることはできません。
ただし、一定の条件を満たし、都道府県知事の許可を得た場合には、建築が認められるケースもあります。

市街化調整区域内における建築は原則禁止とされていますが、都市計画法第43条に基づき、一定の要件を満たす場合には許可されます。
出典:
e-Gov法令検索『都市計画法』
市街化調整区域のメリット
市街化調整区域の多くは、市街地から離れた場所や広大な農地が広がるエリアです。
そのため、生活するには利便性が良いとは言えません。
例えば、スーパーなどの店舗が限られていたり、病院などの医療機関が遠かったりすることがあり、日常生活に不便を感じることがあります。
一方で、市街化調整区域の土地は、市場価値が低い傾向にあるため、比較的安価で購入しやすいというメリットがあります。
さらに、土地の価格が安いことから、固定資産税の負担が軽減される可能性も高くなります。
市街化調整区域のデメリット
市街化調整区域では、建物の規模や用途に関してさまざまな制限が設けられているため、希望通りの建物を建てることが難しい場合があります。
たとえば、新たに建物を建てるだけでなく、既存の建物の建て替えや増改築を行う際にも開発許可が必要です。
このため、許可申請を行うための手続きに時間がかかることがあります。
また、敷地面積に対する建物の建ぺい率や、建物の総床面積に関する容積率などの規制も理解しておく必要があります。

つまり、中古住宅を購入した場合でも、自由に改築を行うことはできない可能性があります。
あわせて読みたいコラム
・建築制限の基本ガイド|高さ制限5種・用途地域14種を初学者向けに解説
開発許可とは?
ここで、開発許可について少し学んでおきましょう。
開発許可とは、一定規模以上の土地開発を行う際に、都道府県や市町村などの自治体から事前に取得しなければならない許可のことです。
これは都市計画法に基づき、無秩序な開発を防ぎ、地域の環境やインフラ整備との調和を図るために定められています。

開発行為とは、土地の形状や用途目的を変更することで、具体的には次のような行為が該当します。
・宅地造成
農地や山林を住宅用の宅地に造成する行為。
・区画の変更
道路や公園などの整備に伴う区画整理。
・建築物の用途変更
住宅を店舗に改装するなど、建物の利用目的を変更する行為。

ちなみに、既存の宅地に家を建てる場合、開発行為には該当しません。
参照サイト
・国土交通省『開発許可制度の概要』
市街化調整区域で住宅購入を検討する際のポイント

市街化調整区域で住宅を購入する際に注意すべきポイントの一つが、住宅ローンの審査です。
これは、区域内の土地は建築制限があるため、金融機関が融資を慎重に判断することがあるためです。

この章では、市街化調整区域がローン審査に与える影響について詳しく見ていきましょう。
建築制限で建物が限定される
市街化調整区域で戸建てを建てる場合、宅地利用が認められた土地に限り建設が可能です。
たとえば、既に建物が建っている土地であれば、宅地利用が認められているため、開発許可を取らずに建設することが可能です。
ただし、建てられる建物には制限があります。
具体的には、都市計画法第34条に基づき、住宅兼用店舗や分家住宅、既存住宅の建て替えなど、特定の用途に限られます。
そのため、自由に建物を建てられるわけではなく、用途が制限されていることを理解しておくことが重要です。
参照コラム
・建築制限の基本ガイド|高さ制限5種・用途地域14種を初学者向けに解説
住宅ローンが通りにくい理由
市街化調整区域で住宅を購入する際、住宅ローンが通りにくくなることがありますが、その主な理由は2つです。
まず、土地には用途制限があり、金融機関が資産価値を低く評価することがあるためです。
次に、住宅を建てるためには原則開発許可が必要で、許可が下りない場合、ローン審査に通らない可能性が高くなります。

そのため、市街化調整区域の土地や建物を購入する際には、住宅ローンに詳しい専門家に相談してみると安心ですね。
住宅ローンについて相談できるサイト
・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!
市街化調整区域で土地を購入する前に知っておくべきポイント
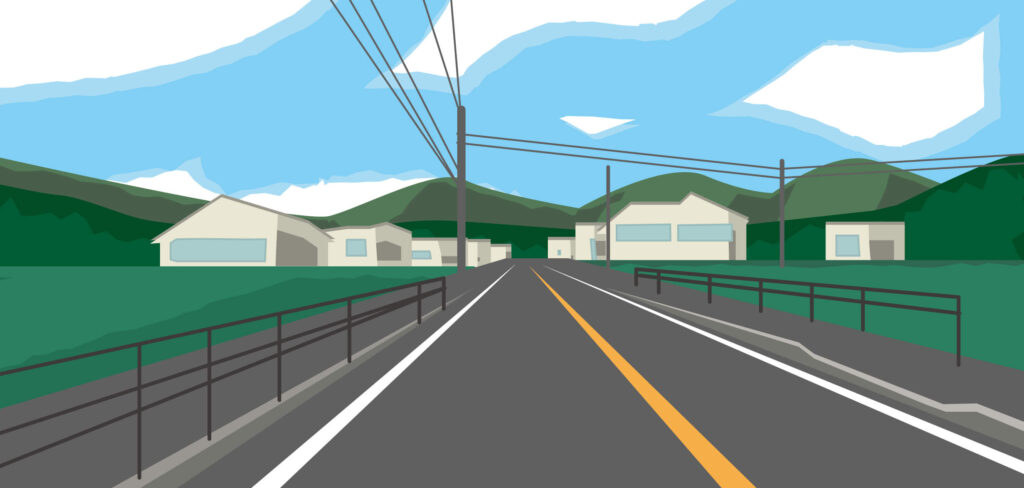
原則として、市街化調整区域では建設などの行為に制限があることはご理解いただけたかと思います。
ただし、この規制は自治体ごとに異なる場合があります。

では最後に、市街化調整区域での注意点を確認しておきましょう。
地域による規制の違い
市街化調整区域の規制は、全国一律ではなく、自治体や地域ごとに異なります。
たとえば、ある地域では一部の開発が認められる一方で、別の地域ではより厳しい制限が設けられていることもあります。
そのため、市街化調整区域の詳細を理解するには、市街化区域や非線引き区域との違いもあわせて確認しておくことが大切です。

市街化区域や非線引き区域の違いについては、以下のコラムで詳しくまとめています。
あわせて読みたいコラム
・都市計画法が実務に与える影響とは?土地活用のアイディアを探る!
市街化調整区域での土地活用例
市街化調整区域での土地活用法には、以下4つの方法などがあります。
①農業地・田園での活用
②太陽光発電
③物流施設や倉庫
④駐車場
第一章でもお伝えしましたが、市街化調整区域での土地活用には、原則として開発許可が必要です。
活用方法によっては事前に自治体との相談が求められるため、規制を確認しながら適切な手続きを進めることが重要です。

計画段階で情報をしっかりと収集し、スムーズに活用できるよう準備しておきましょう。
まとめ
今回の記事のまとめです。
市街化調整区域は、農地や自然環境を保護するために開発が制限された区域です。
原則として新たな建物を建てることはできませんが、一定の条件を満たせば都道府県知事の許可を得て建築することも可能です。
土地は固定資産税の負担が抑えられるというメリットがありますが、商業施設や医療機関が少ないため、生活の利便性が低い点には注意が必要です。