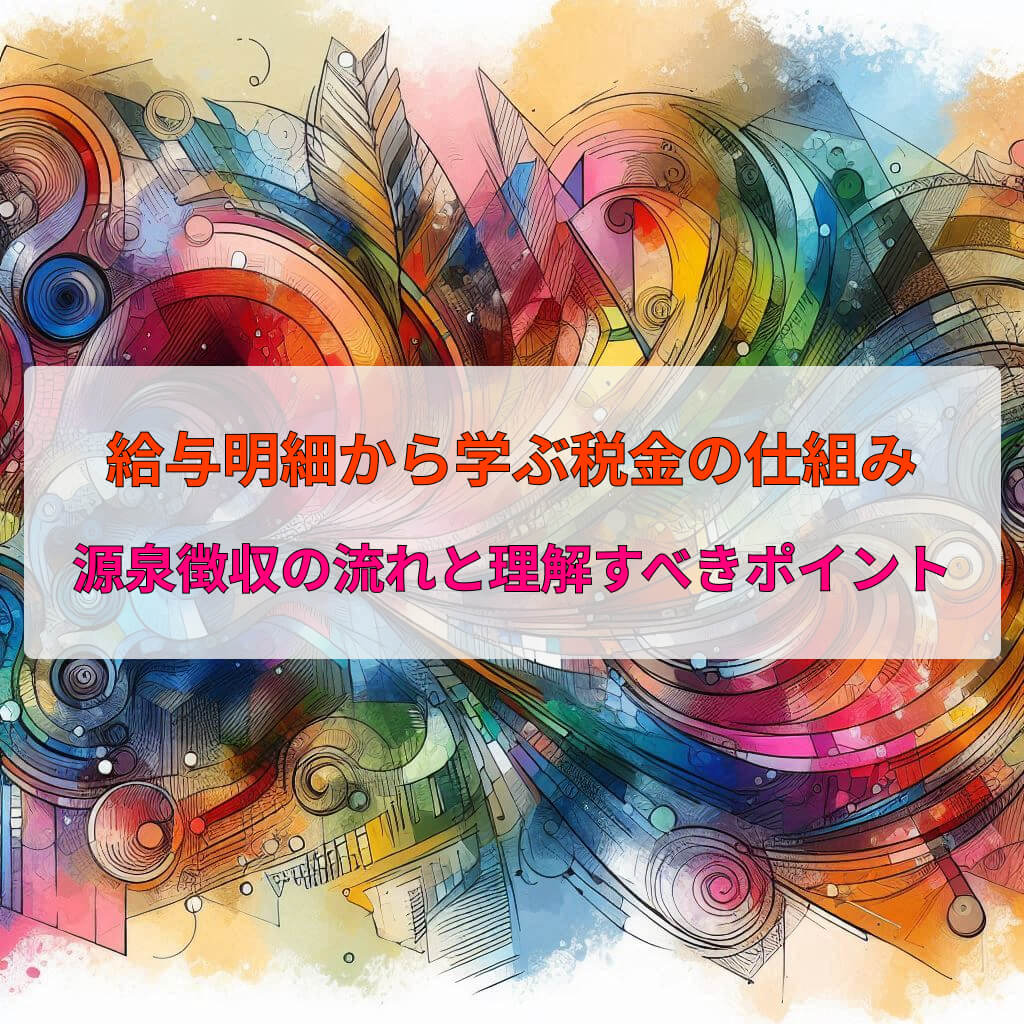『給与明細はどこをチェックすればいいの?』
会社員などの給与所得者は、税金の支払いを「源泉徴収」という形で行っています。
これは、会社が従業員の給与からあらかじめ税金を差し引き、そのまま税務署へ納付する仕組みです。
これにより、給与所得者自身が税金の計算や納付手続きを行う必要がなく、納税に関する事務的な負担が軽減されます。
この記事では、給与明細に表示されている項目の内訳や、源泉徴収の仕組みについて詳しくご紹介します。
この記事で分かること
- 源泉徴収の仕組み
- 給与明細に記載される税金の種類と内容
- 源泉徴収によるメリットと注意点

納税額や社会保険料を把握することは、家計の見直しにつながりますよ!
給与所得と源泉徴収の基本

給与所得と源泉徴収――
これらの言葉はよく耳にするものの、その具体的な内訳や仕組みについては、意外と理解していない方も多いかもしれません。
まずは、この2つの基本的な概要から見ていきましょう。

「収入」と「所得」の違いをしっかりと理解しながら、それぞれの特徴をおさらいしていきましょう。
そもそも、給与所得とは?
給与所得とは、企業や雇用主から支払われる給与収入から、各種控除を差し引いた後に残る実際に課税対象となる所得のことです。

給与所得の主なポイントは、以下の3つです。
①社会保険料の控除
給与から、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料が控除されます。
②給与所得控除の適用
給与所得者には、収入に応じた一定額の給与所得控除が適用され、課税対象となる所得が軽減されます。
③源泉徴収制度の適用
雇用主が従業員の給与から所得税を天引きし、納付するため、原則として納税が自動的に完了します。

給与収入と給与所得はよく混同されますが、給与収入は会社から支払われる給与や賞与の総額です。
給与所得に関する情報サイト
・No.1400 給与所得|国税庁
源泉徴収制度とは?
源泉徴収制度とは、企業や団体などの支払者が、給与や報酬などの支払い時に、受取者に代わって税金を天引きし、税務署に直接納める仕組みです。
この制度により、会社員の場合は、毎月の給与から所得税が差し引かれ、納税が完了します。
ただし、税額に過不足がある場合は、年末調整によって精算されます。
また、源泉徴収制度は、給与所得に限らず、報酬や配当、年金などの所得にも適用されます。

給与明細に記載されている所得税は、源泉徴収によって天引きされた金額です。
あわせて読みたいコラム
・可処分所得ってどんなもの?シミュレーションで学ぶ手取り増加法
給与明細に表示される項目とは?
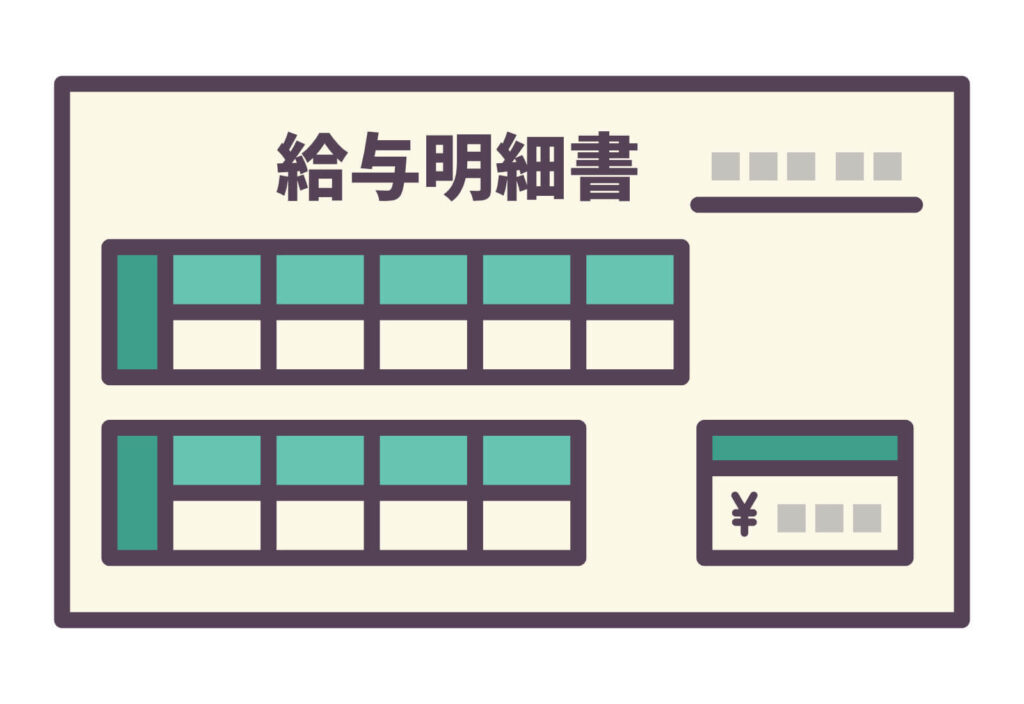
一般的に、給与明細には基本給をはじめ、所得税、住民税、健康保険料など、さまざまな項目が記載されています。

この章では、給与明細に記載されている主な項目について見ていきましょう。
基本給
基本給とは、従業員が労働の対価として支払われる最も基本的な給与の部分です。
通常、基本給は雇用契約に基づいて定められ、職務内容や勤務時間に応じて支払われる金額が異なります。

基本給の特徴は、以下の3つにまとめることができます。
①定額の支給
基本給は通常、月ごとに定額で支給され、労働時間や勤務日数に関係なく一定額が支払われます。
➁昇給の基準
基本給は従業員の昇給基準となることが多く、定期的な昇給が行われる場合、基本給が引き上げられることが一般的です。
③社会保険や税金の計算基準
基本給は、健康保険料、厚生年金、所得税などの社会保険料や税金を算出する際の基準となります。
参照コラム
・標準報酬月額ってどうやって求めるの?基本給・賞与・手当の詳細解説
手当て
手当は基本給に加えて支給される追加の金額で、労働内容や勤務条件に応じて異なります。

手当には、以下5つのような種類があります。
①通勤手当
交通費として支給される手当で、会社までの通勤にかかる費用を補助する目的で支給されます。
➁残業手当
定められた勤務時間を超えて働いた場合に支払われる手当で、通常、時間外勤務の対価として支給されます。
③役職手当
特定の職位にある社員に対して支給される手当で、役職の責任や重要度に応じて金額が異なります。
④家族手当
扶養家族がいる社員に支給される手当で、家族構成に応じて支給額が異なる場合があります。
⑤資格手当
業務に必要な資格を有している場合に支給される手当で、特に専門的な資格を有する場合に多く支給されます。

なお、⑤の資格取得にかかる費用は、公的制度で負担することができますよ。
あわせて読みたいコラム
・特定支出控除の対象となる経費とは?資格取得費や通勤費などを解説
控除項目
給与明細に記載されている控除項目は、主に法定控除と任意控除の2つに分類されます。
Ⓐ法定控除
法定控除とは、法律や制度に基づき、企業が必ず差し引かなければならない控除項目です。

法定控除として、以下の5つが挙げられます。
①所得税
従業員の給与に基づいて課税される税金で、源泉徴収によって支払われます。
➁住民税
地方自治体に納付する税金で、前年の収入に基づいて課税され、毎月給与から引かれます。
③健康保険料
健康保険制度に加入するための保険料で、病気やケガの医療費を補うために支払います。
④厚生年金保険料
公的年金制度の一部で、将来の年金受給に向けて支払う保険料です。
⑤雇用保険料
失業時に支援を受けるための保険料で、雇用保険に加入している場合に支払います。
Ⓑ任意控除(企業や従業員の選択に基づく控除)
一方で、任意控除とは、企業の福利厚生制度や従業員の選択に基づき、必要に応じて差し引かれる控除項目です。、

任意控除として、以下の6つが挙げられます。
①個人年金保険料
従業員が加入している個人年金保険の保険料が給与から差し引かれます。
➁財形貯蓄の掛金
企業が提供する財形貯蓄制度に参加している場合、その掛金が給与から控除されます。
③共済掛金
企業が提供する共済制度に加入している場合、その掛金が給与から控除されます。
④社員積立金
企業が導入している積立金制度に基づき、従業員の給与から一定額が差し引かれる場合があります。
⑤寮費・食費
企業が提供する寮に住んでいる場合、寮費や食費が給与から差し引かれることがあります。
⑥交通費
企業が交通費を支給している場合、給与に交通費が含まれているか、逆に交通費が差し引かれる場合もあります。
給与明細からわかる税金のしくみ

給与明細を受け取ると、つい手取り額だけに目がいきがちですが、他の項目もしっかり理解することで、毎月の収支バランスを改善する手助けとなります。
FPに無料相談できるサイト
・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!
手取り額に与える影響
給与明細には、税金や社会保険料がどのように差し引かれているかが記載されており、これらが手取り額に与える影響を理解する手がかりとなります。
特に、控除額については、適切な知識を持つことが大切です。
例えば、所得税や住民税、健康保険料、厚生年金保険料などの計算方法を把握することで、税金や社会保険料の負担を減らす方法が見えてきます。

手元に残るお金、いわゆる生活費に使える部分を『可処分所得』と言います。
あわせて読みたいコラム
・可処分所得ってどんなもの?シミュレーションで学ぶ手取り増加法
可処分所得を増やすための実践的な方法
可処分所得を増やすポイントとして、以下3つの要素が挙げられます。
①支出を減らす
②控除額を増やす
③収入を上げる
可処分所得を増やすには、まず支出の見直しが重要です。
生活費の節約や支出の最適化を行うことで、手元に残るお金を確保できますし、そのために、公的制度を活用することが効果的です。
さらに、収入源の増加も可処分所得を増やす大きな要素となります。

収入を急に増やすのは難しいかもしれませんが、支出の削減は取り組みやすいですよね。
あわせて読みたいコラム
・ライフハックで毎月1万円の貯蓄法とは?可処分所得を増やすための実践
まとめ
今回の記事のまとめです。
給与所得とは、企業から支払われる給与や賞与から社会保険料や税金を差し引いた後、実際に課税対象となる所得を指します。
また、源泉徴収制度では、企業が従業員の給与から税金を天引きし、その税金を税務署に納付します。
給与明細に記載された税金や社会保険料を理解することは、手取り額を増やすための大切なステップです。