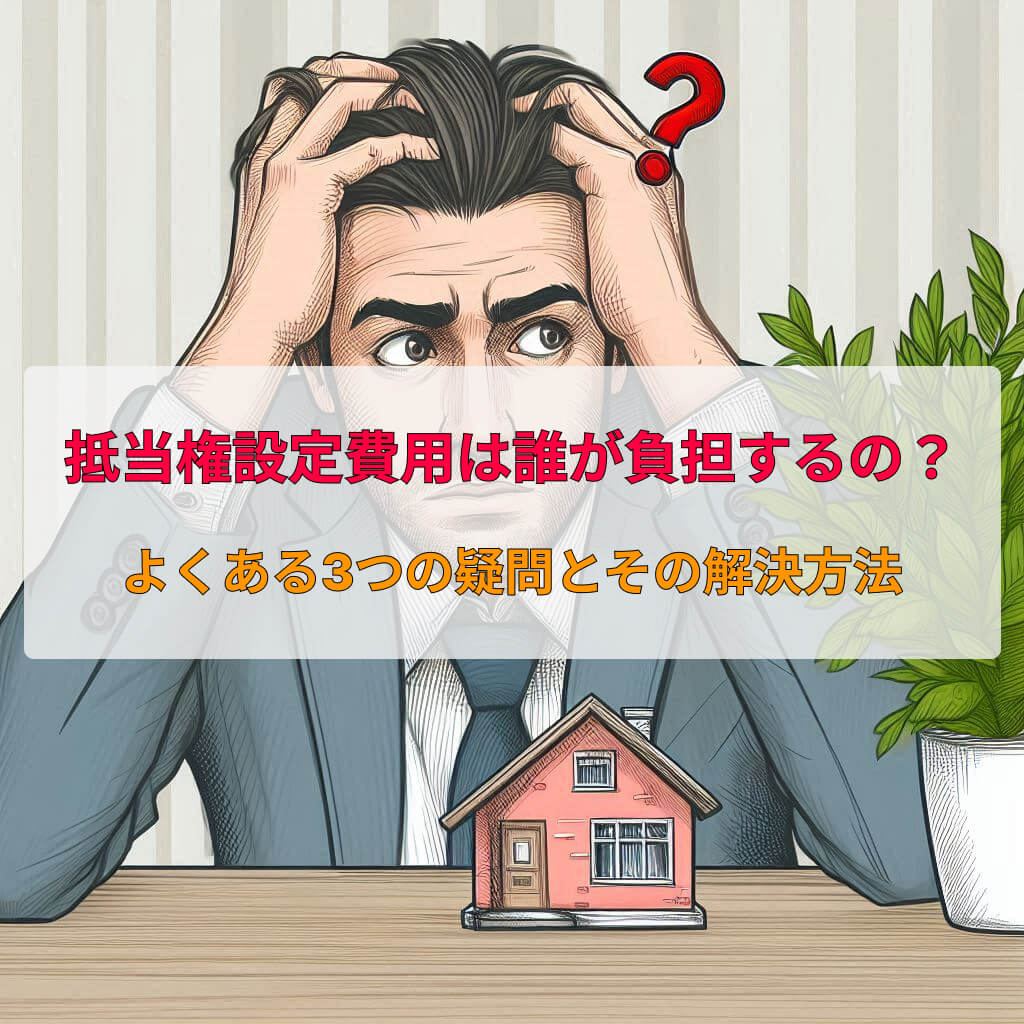不動産を購入する際、住宅ローンを利用する多くの方が経験するのが「抵当権の設定」ですよね。
日常生活ではあまり聞き慣れない言葉ですが、ローン返済に関わる重要な手続きのひとつです。
一般的にこの手続きには、登録免許税や司法書士への報酬など、さまざまな費用が発生しますが、
”これらの費用は誰が負担するの?”と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、抵当権の基本から費用の内訳、よくある質問までをわかりやすく解説していきます。
この記事で分かること
- 抵当権の基本的な仕組み
- 抵当権設定にかかる具体的な費用の内訳
- 費用負担や手続きに関するよくある疑問

章の後半では、抵当権設定の実例やよくある疑問をまとめていますよ。
共有持分や空き家など、
売却に悩んでいる方必見!
\まずは簡単入力で無料査定してみる👇/
抵当権とは?基本をわかりやすく解説

そもそも、抵当権とは何を指すのでしょうか?
抵当権とは、債権者がローン返済の滞納に備え、不動産などを担保として契約を結ぶ権利のことです。

まずは、抵当権の基本的な特徴を確認していきましょう。
税金のこと、よくわからない…
そんな方でも安心👌
\税理士がオンラインで無料相談👇/
どの税理士に相談していいのか悩んでいる方へ👇
・税理士紹介ネットワーク
抵当権の役割
抵当権(ていとうけん)とは、お金を貸した人(債権者)が、万が一返済がされなかったときに備えて、不動産などの財産を担保として確保する権利です。
設定は義務ではありませんが、住宅ローンなど高額な融資では、金融機関が貸し倒れリスクを避けるために求めるのが一般的です。
抵当権設定における2つの役割
①債権者の保護
貸したお金が返済されない場合でも、債権者は不動産を競売にかけて代金から回収できます。
②債務者の信用力向上
不動産を担保にすることで、債務者はより有利な条件で融資を受けやすくなります。
なぜ抵当権の設定が必要なのか
先ほどの役割について、もう少し掘り下げてみます。
抵当権の設定は、債権者(お金を貸す側)の権利を守るだけでなく、債務者(お金を借りる側)にとっても、資金調達の選択肢を広げるというメリットがあります。

債権者・債務者それぞれのメリットを2つずつ見てみましょう。
債権者側のメリット
債権者側のメリットとして、主に以下の2点が挙げられます。
①万が一返済されなかった場合に担保不動産を売却して回収できる
返済が滞った場合でも、抵当権によって担保不動産を差し押さえ、競売によって債権を回収することができます。
②貸し倒れリスクの軽減
担保があることで債務不履行時のリスクが減り、安心して融資を行うことができます。
債務者側のメリット
一方で、債権者側の主なメリットとして、以下の2点が挙げられます。
①金利を抑えられる可能性がある
不動産などを担保にすることで、無担保よりも信用度が上がり、比較的低金利での借り入れが可能になります。
②高額な融資を受けやすくなる
担保があることで貸し手の安心感が増し、無担保よりも大きな金額を借りることができます。

なお、抵当権は、物件や契約条件によって借入額が変わる場合があります。
賃貸経営に関わる悩みは、不動産のプロに相談するのも一つの方法です。
賃貸経営の頼れるパートナーは👇
一心企画
抵当権の設定にかかる費用とは

住宅を購入したことがある方であれば、抵当権の費用について「誰がどれくらい支払うのか」イメージがつくかもしれません。

この章では、初めて抵当権を設定する方向けに、設定時にかかる費用の内訳について見ていきましょう。
共有持分や長期間の空き家など、
売却に困る不動産の悩みを解決!
\簡単入力で、まずは無料査定👇/
不動産売却を検討したい方へ👇
・困った不動産の売却なら「ワケガイ」
抵当権設定にかかる主な費用
抵当権を設定する際には、主に以下3つの費用が発生します
①登録免許税
②その他費用
③司法書士費用

上記3つについて、それぞれ見てみましょう。
1. 登録免許税
抵当権を設定する際には、法務局に対して登録免許税を納める必要があります。
住宅ローンなどの一定の条件を満たす場合、租税特別措置法により、税率が0.1%(1000分の1)に軽減されることもあります。
ただし、原則として、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率は次の通りです。
抵当権設定登記にかかる登録免許税額 = 住宅ローンの借入額 × 0.4%
参照サイト
・国税庁『No.7191 登録免許税の税額表』
2. その他費用
登録免許税は大きな費用の一つですが、抵当権を設定する際にはその他の費用も考慮する必要があります。
その他の費用として、以下の4つの項目が挙げられます。
①収入印紙(金銭消費貸借契約書用)
②登記事項閲覧費用
③登記事項証明書
④印鑑証明書 など

なお、①は数千円から数万円の範囲で、②③④はそれぞれ数百円程度を目安としておきましょう。
3. 司法書士に依頼する場合の報酬相場
抵当権の設定は、一般的に司法書士に依頼するのが通例です。
その理由は、自己申請で抵当権設定登記を行う際、金融機関との共同申請が必要となり、金融機関側のリスクが高いため、許可が下りにくくなるからです。
司法書士に依頼する際の費用は事務所ごとに異なりますが、一般的な相場は3万円〜10万円程度とされています。
司法書士に相談できるサイトは👇
・全国¥0相談はこちら!【アース司法書士事務所】
登録免許税の実例
登録免許税の実例を一つ見てみましょう。
たとえば、3,000万円の住宅ローンを借り入れ、抵当権を設定する場合、登録免許税は以下のように計算されます。
登録免許税額 = 借入額 × 税率(0.4%)
3,000万円 × 0.004(=0.4%)= 12万円
ただし、これはあくまで登録免許税のみの費用です。
前章で解説したとおり、司法書士への依頼費用や印紙代など、その他の費用も別途かかる点に注意が必要です。

ちなみに、各仕業には業務範囲が決まっているため、その範囲も確認しておきましょう。
あわせて読みたいコラム
・遺産分割協議書の作成費用の相場は?4つの専門家ができることと費用比較
抵当権設定費用に関するよくある疑問

抵当権を設定する際、さまざまな疑問が生じることがあります。
そこで最後に、抵当権設定費用についてよくある疑問を整理してみます。

抵当権に関する疑問を3つ、一緒に解決していきましょう!
税金のこと、よくわからない…
そんな方でも安心👌
\税理士がオンラインで無料相談👇/
どの税理士に相談していいのか悩んでいる方へ👇
・税理士紹介ネットワーク
住宅ローンを完済した後も抵当権は残るの?
住宅ローンを完済すると、抵当権そのものは消滅します。
これはローンの支払いが終了することで、担保として設定された抵当権も無効になるためです。
しかし、抵当権が消滅しても登記上では自動的に抹消されないため、法務局で抵当権抹消登記の手続きを行う必要があります。
抵当権の抹消にも費用はかかる?
抵当権を抹消する際には費用がかかります。
目安として、1つの不動産につき1,000円程度です。
ただし、司法書士などの専門家に依頼する場合は別途料金が発生します。
また、登記に必要な謄本や証明書の取得費用も必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。
抵当権設定にかかる費用はローン契約に含まれるの?
基本的に、抵当権設定費用はローン契約に含まれておらず、別途支払う必要があります。
ただし、金融機関によっては、手数料や登記費用をローンの一部として融資額に組み込むことができる場合もあるため、契約時にその詳細を確認しておくことが大切です。

住宅ローンを組む際には、一度専門家に相談してみましょう。
知識・準備不要でOK👌
はじめての家計・保険相談を
\FPにオンライン無料相談👇/
住宅ローンに関する相談先は👇
・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!
まとめ
今回の記事のまとめです。
抵当権設定には、登録免許税、その他の費用、司法書士費用の3つがかかります。
さらに、住宅ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、その抹消手続きには別途費用がかかることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。