ふるさと納税を利用したいと思っても、申請手続きに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが、「ワンストップ特例制度」です。
この制度を利用すれば、確定申告をせずに税金の控除を受けることができます。
この記事では、ワンストップ特例制度の概要や申請方法、活用のポイントについてわかりやすく解説します。
この記事で分かること
- ワンストップ特例制度の特徴
- 申請方法と手続きの流れ
- 制度を活用する際のポイント

会社員の方がこの制度をどのように活用できるのか、具体的に見ていきましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を利用した場合に、確定申告をせずに税金の控除を受けることができる制度です。

まずは、ワンストップ特例制度の基本的な特徴を見ていきましょう。
ワンストップ特例制度の基本概要
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を利用する際の手続きを簡素化する制度です。
ワンストップ特例制度の4つの特徴
①申請手続きがシンプル
申請手続きは、申請書と必要書類を提出するだけで完了します。
➁寄付先の上限が設定されている
寄付先が5自治体以内であれば利用可能です。
(※1自治体に複数回寄付しても1自治体としてカウントされます)
③確定申告が不要
特例申請書を寄付先の自治体に提出することで、税額控除が適用されます。
④控除が住民税に反映される
寄付額に応じた控除額が、翌年度6月以降の住民税に直接反映されます。

ふるさと納税の概要については、以下のコラムで詳しくまとめていますよ!
参照コラム
・個人事業主向け!ふるさと納税の節税メリットと注目自治体の特徴解説
ワンストップ特例制度が便利な理由
ワンストップ特例制度が便利な理由として、主に次の3つが挙げられます。
①手続きにかかる負担の軽減
確定申告が不要なため、税務署への書類提出や専門知識がなくても手続きができ、ふるさと納税を気軽に利用できます。
➁計画的に寄付できる
寄付先が5自治体までに制限されるため、予算内で寄付額を調整しやすく、過剰な寄付を避けることができます。
③自治体との関係構築
寄付先が5自治体に限定されることで、長期的な支援意識が高まり、自治体との関係を深めやすくなります。
ワンストップ特例制度の適用条件
ワンストップ特例制度の適用条件には、以下3つの項目が挙げられます。
①申請期限を守る
ワンストップ特例制度を利用するためには、寄付を行った年の翌年1月10日までに必要書類を提出する必要があります。
➁寄付先が5自治体以内であること
ワンストップ特例制度は、年間の寄付先が5自治体以内の場合に適用されます。
③必要書類を正確に提出する
寄付先から送付される「寄付金受領証明書」と「ワンストップ特例申請書」の2つを必要期限内に提出することが求められます。

③には、本人確認書類の提出も必要です。
参照サイト
・ワンストップ特例制度とは?手続きの流れ・期限・特例申請書の書き方を解説! | ふるさと納税サイト「さとふる」
ワンストップ特例制度の申請方法
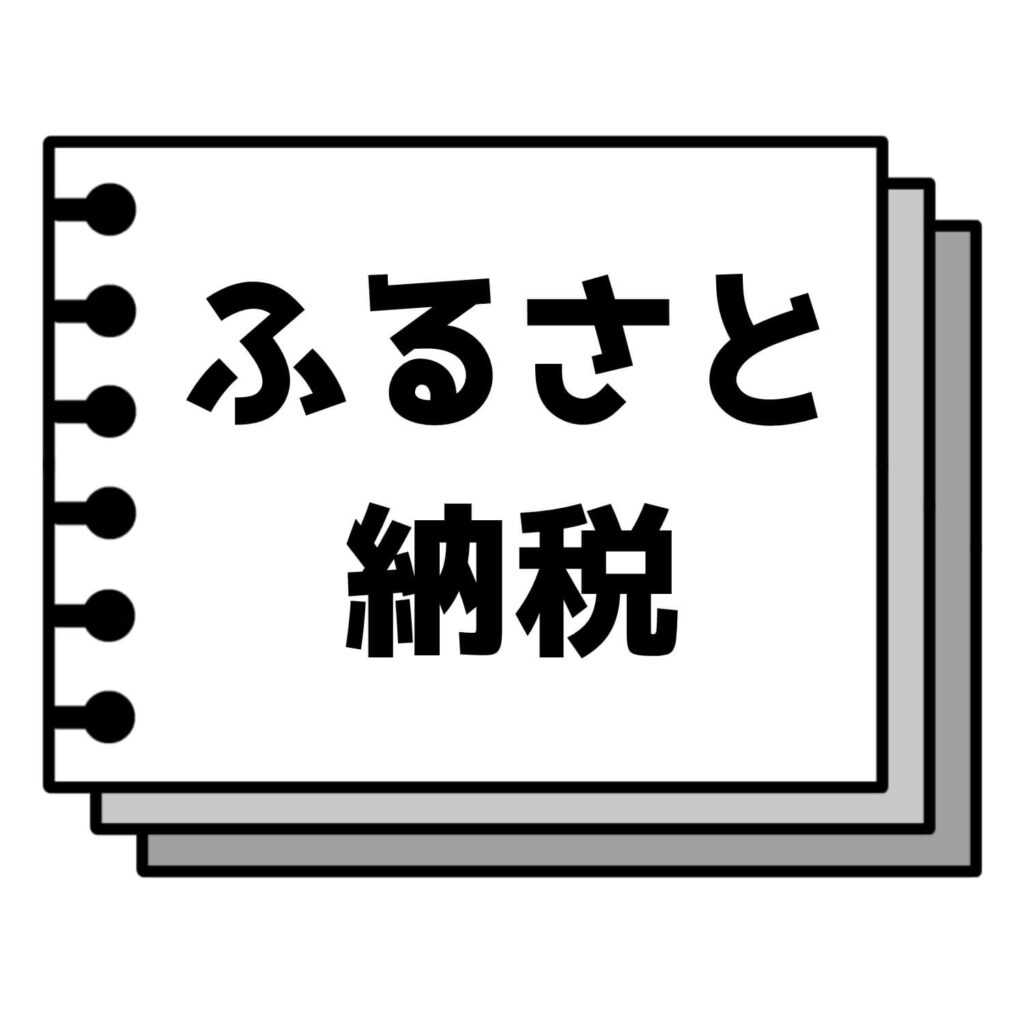
先ほど触れたように、ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに申請書を提出する必要があります。

次に、ワンストップ特例制度の申請方法について見ていきます。
ワンストップ特例制度の申請手順
ワンストップ特例制度の申請は、次の4つのステップに沿って行います。
1. ふるさと納税を行う
まず、ふるさと納税を行いたい自治体を選定します。
2. ワンストップ特例申請書を入手
ふるさと納税後、自治体から「ワンストップ特例申請書」が送付されるか、インターネット寄付の場合はオンラインでダウンロードできます。
3. 申請書の記入
申請書に必要事項を記入します。記入内容は、氏名、住所、生年月日、寄付額などです。
4. 本人確認書類の準備
申請書に添付する本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピーを準備します。
5. 申請書と本人確認書類を提出
必要書類をそろえたら、申請書と本人確認書類を寄付先の自治体に郵送し、提出期限は寄付した年の翌年1月10日までです。
申請時の注意点と確認方法
ワンストップ特例制度の申請時の注意点と確認方法を、それぞれ以下にまとめます。
Ⓐ申請時の注意点
申請時の注意点として、ワンストップ特例申請書にはマイナンバーの記載が必要です。
ただし、申請書に記入漏れや不備があると受理されないことがあるため、提出前に内容を十分に確認しましょう。
また、一度提出した申請書は変更できないため、誤りがあった場合は確定申告で訂正する必要があります。
Ⓑ申請後の確認方法
申請受理通知書は、ワンストップ特例申請書を提出した本人の住所宛に自治体から送られます。
もし通知が届かない場合は、速やかに自治体に問い合わせることが大切です。
また、寄付金に対する控除は翌年度6月以降の住民税に反映されるため、住民税の通知書で控除額が正しく反映されているか確認しましょう。
ワンストップ特例制度を活用するためのポイント

ワンストップ特例制度を最大限に活用するためには、年収に応じた寄付額の上限を把握し、寄付金控除に関する正しい知識を持つことが大切です。

最後に、これらのポイントを押さえたうえで、他の控除との併用の重要性について解説します。
年収に応じた寄付額の目安とは?
ふるさと納税を利用する際、寄付金に対する税額控除には上限があります。
この上限額は、寄付者の年収(所得)、家族構成、すでに受けている税金の控除によって決まります。
扶養家族を考慮しない場合の年収別の寄付額目安は、それぞれ以下となります。
年収300万円:
寄付額の上限は約3万円~4万円
年収500万円:
寄付額の上限は約5万円~6万円
年収800万円:
寄付額の上限は約8万円~9万円
年収1000万円:
寄付額の上限は約10万円~12万円

実際の寄付額の上限は、年収や所得、家族構成などによって異なります。
詳細については、以下のシミュレーションサイトをご活用ください。
ふるさと納税の限度額を計算!控除上限額シミュレーション | ふるさと納税サイト「ふるなび」
その他の控除との併用
ふるさと納税の寄付による税控除は、他の税控除と併用することが可能です。
併用することで、税金の還付や控除を最大化できるため、効率的に税負担を軽減できます。
税控除とその他の控除のポイント
1. 医療費控除
医療費控除は、一定額以上の医療費を支払った場合に、その支出額の一部を所得から控除できる制度。
2. 生命保険料控除
生命保険に加入している場合、支払った保険料の一部を所得から控除できる。
3. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に受けられる控除で、年末のローン残高に応じた額を所得税から控除できる。

その他の控除についても、正しい知識を身につけておくことが大切ですよ。
あわせて読みたいコラム
・個人事業主の節税メリットを活用する確定申告のポイント
まとめ
今回の記事のまとめです。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を利用する際に、確定申告を行わずに税額控除を受けられる簡便な制度です。
この制度を利用することで、寄付額に応じた控除が翌年度の住民税に反映されます。
利用には、寄付年の翌年1月10日までに必要書類を提出することが求められ、寄付先は5自治体以内に限られます。

