セルフメディケーション税制とは、健康維持や病気予防のために自身で購入した医薬品に対して、税金の軽減を受けられる制度です。
しかし、実際にどのような仕組みで、どんなメリットがあるのかについては、詳しく理解している方は少ないかもしれません。
本記事では、セルフメディケーション税制の基本的な内容から、利用の要件、具体的な活用方法までを、わかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- セルフメディケーション税制の特徴
- どのような医薬品が対象となるのか
- セルフメディケーション税制の活用方法

最後の章では、実際の活用例についてもご紹介していますよ!
FPに無料相談できるサイト
・【マネードットコム】
セルフメディケーション税制とは?
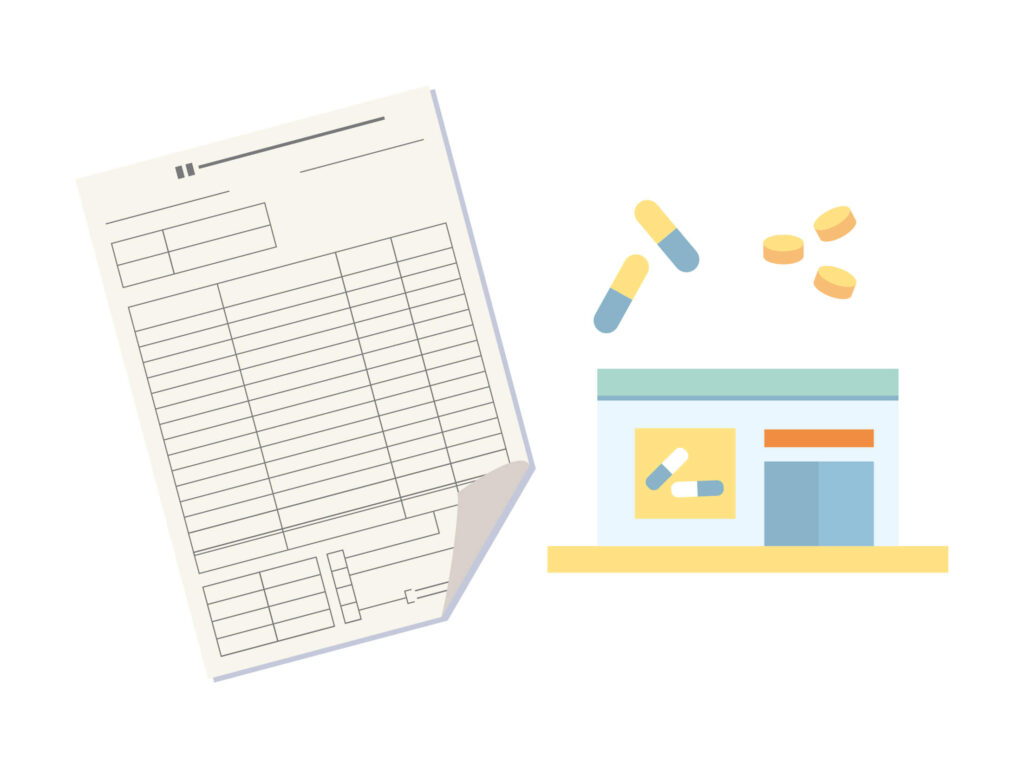
まず初めに、セルフメディケーション税制の概要を見ていきましょう。
この制度は、日常的にはあまり耳にすることがないかもしれませんが、この制度を利用することで、健康維持や病気予防に役立つ医薬品を購入した費用を、自身の所得税から軽減できます。

通常の医療費控除と、どのような点が異なるのかを確認していきましょう。
セルフメディケーション税制の概要
セルフメディケーション税制とは、健康維持や病気予防のために購入したOTC(市販)医薬品に対し、一定の条件を満たすことで税金の軽減を受けることができる制度です。
セルフメディケーション税制の3つのポイント
①対象となる医薬品
セルフメディケーション税制の対象となるのは、市販薬(OTC薬)です。例えば、風邪薬や胃腸薬、ビタミン剤などが含まれますが、医師の処方が必要な薬は対象外となります。
②控除額
対象となる医薬品の購入金額が12,000円を超えた場合、その超過分に対して一定の金額が控除され、年間で最大88,000円の税金軽減を受けることができます。
③利用条件
利用者は、一定の健康診断や予防接種を受けている必要があり、健康維持や病気予防への積極的な取り組みが求められます。

なお、税制の対象になるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
参照サイト
厚生労働省:『2 セルフメディケーション税制対象品目一覧』
セルフメディケーション税制のメリットとデメリット
セルフメディケーション税制を活用することで、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
①税金の軽減
OTC医薬品を購入した費用を申告することで、所得税や住民税の軽減を受けられ、経済的なメリットが得られます。
②健康管理の促進
病気の予防や早期発見に役立つ医薬品を購入することは、予防医療への意識を高めるきっかけとなります。
③申告手続きの簡便さ
購入した医薬品の領収書を保管し、確定申告で申請するだけで手続きが完了するため、負担が少なく手軽に利用できます。
デメリット
①対象となる医薬品が限られている
すべてのOTC医薬品が対象となるわけではなく、厚生労働省が指定した一定の医薬品に限られます。
②年額12,000円の購入費が必要
制度を利用するためには、年間で12,000円以上のOTC医薬品を購入する必要があります。
③医療費控除との併用不可
セルフメディケーション税制は、医療費控除と同時に利用できないため、どちらか一方を選んで活用する必要があります。
あわせて読みたいコラム
・医療費控除の適用範囲と活用法|個人事業主向け確定申告のポイント
どのような人が対象なの?

セルフメディケーション税制を活用するうえで気になるのが、適用条件です。
特に、健康増進や病気予防のための一定の取り組みが求められる点も大切なポイントの一つです。

この章では、制度を利用するための3つの条件について確認していきましょう。
セルフメディケーション税制を利用するための3つの条件
セルフメディケーション税制を利用するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1. 対象医薬品を年間12,000円以上購入していること
対象となる医薬品の購入額が一定額を超えた場合に適用されます。
チェックポイント
・厚生労働省が指定する「スイッチOTC医薬品」を購入し、年間の合計額が12,000円を超えることが必要。
・上限は88,000円まで。
2. 健康の維持・増進のための取り組みを行っていること
以下の5つの特定の健康管理を行っていることが条件となります。
・予防接種(インフルエンザ予防接種など)
・健康診断(定期健康診断、人間ドック)
・がん検診
・特定健康診査(メタボ健診)
・勤務先の健康診断 など

なお、上記のいずれか一つに該当すればよいため、すべてを受ける必要はありません。
3. 確定申告を行うこと
適用を受けるには確定申告が必要です。
必要書類は以下の3点です。
①対象医薬品の購入レシートや領収書(「セルフメディケーション税制対象」の記載があるもの)
②健康診断や予防接種の証明書
③確定申告書

所得税および住民税を適切に納税していることも、適用条件の一つですよ!
世帯合算できるの?
セルフメディケーション税制では、健康診断や予防接種などの一定の取り組みを行っている場合、生計を一にする親族(配偶者や子供など)が購入したOTC医薬品の費用も合算して申告できます。
そのため、合算した購入金額が12,000円(税込)以上であれば、控除の対象となります。
世帯合算のワンポイント
・合算できるのは、同一生計の親族(配偶者や子供など)の購入費用。

控除について気になることがあれば、FPに相談してみましょう。
FPに無料相談できるサイト
・生命保険の無料相談サービス【マネードットコム】
セルフメディケーション税を活用するための注意点

これまでお伝えしてきた通り、申告時には、対象となる医薬品を購入したことを証明するため、購入した医薬品の領収書や明細書を保管しておくことが大切です。

最後に、申告時に押さえておきたいポイントを確認しましょう。
医療費控除との併用はできない
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例の一つであり、従来の医療費控除とは併用できません。
このため、どちらか一方を選んで利用する必要があります。
従来の医療費控除は、病院での診察や治療、薬代などの医療費が年間10万円を超えた場合、その超過分を所得控除として申告できる制度です。
医療費控除の対象には、病院での治療費や処方された医薬品代、さらに治療に関連するその他の費用も含まれます。

つまり、医療費控除は適用範囲が広く、所得控除として多くの医療費が対象となるということです。
あわせて読みたいコラム
・セルフメディケーション税制はどんな人向き?医療費控除との節税比較
結局どのくらい節税につながるの?
お伝えしてきた通り、対象となる医薬品等の購入費が12,000円を超えた場合、控除の対象となります。

ここで、以下の具体例をもとに、実際の減税額を計算してみましょう。
具体例:
OTC医薬品を年間60,000円購入した場合
対象金額の計算
控除対象となる金額 = 60,000円 - 12,000円 = 48,000円
所得税の計算
控除額48,000円 × 所得税率20% = 9,600円(所得税還付分)
住民税の計算
控除額48,000円 × 住民税率10% = 4,800円(住民税減額分)
最終的な減税額
9,600円(所得税還付分) + 4,800円(住民税減額分) = 14,400円
この場合、年間60,000円のOTC医薬品購入による減税額は、14,400円となります。

自身の具体的な節税額を確認したい場合は、シミュレーションサイトを活用してみましょう。
シュミレーションが行えるサイト
・『どれだけおトク? ~計算してみよう!~』
まとめ
今回の記事のまとめです。
セルフメディケーション税制は、健康維持や病気予防のために購入した市販薬(OTC薬)の費用について、一定の条件を満たすことで所得税の軽減を受けられる制度です。
主な適用条件
- 対象医薬品を年間12,000円以上購入すること。
- 健康維持・増進の取り組みを行っていること。
- 確定申告を行うこと。
これらの条件を満たすことで、最大88,000円の所得税の軽減を受けることができます。


