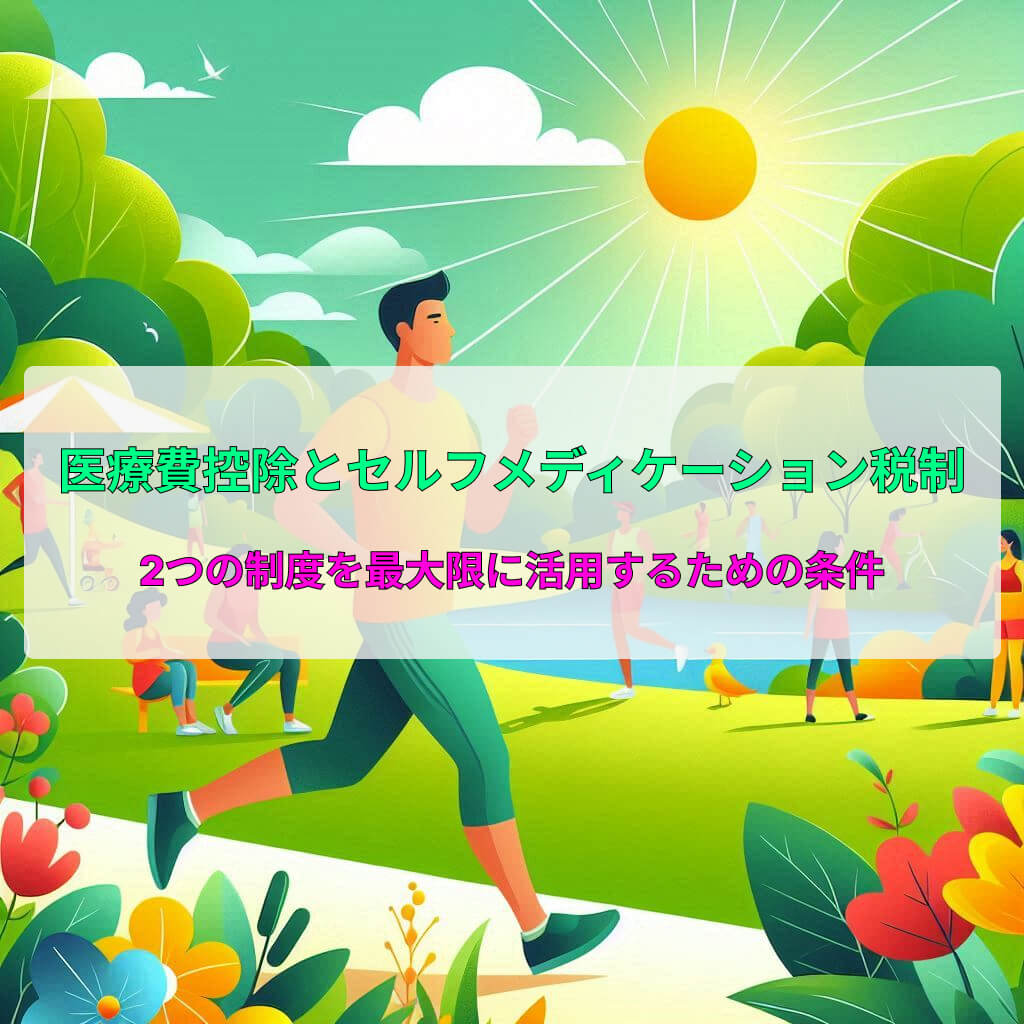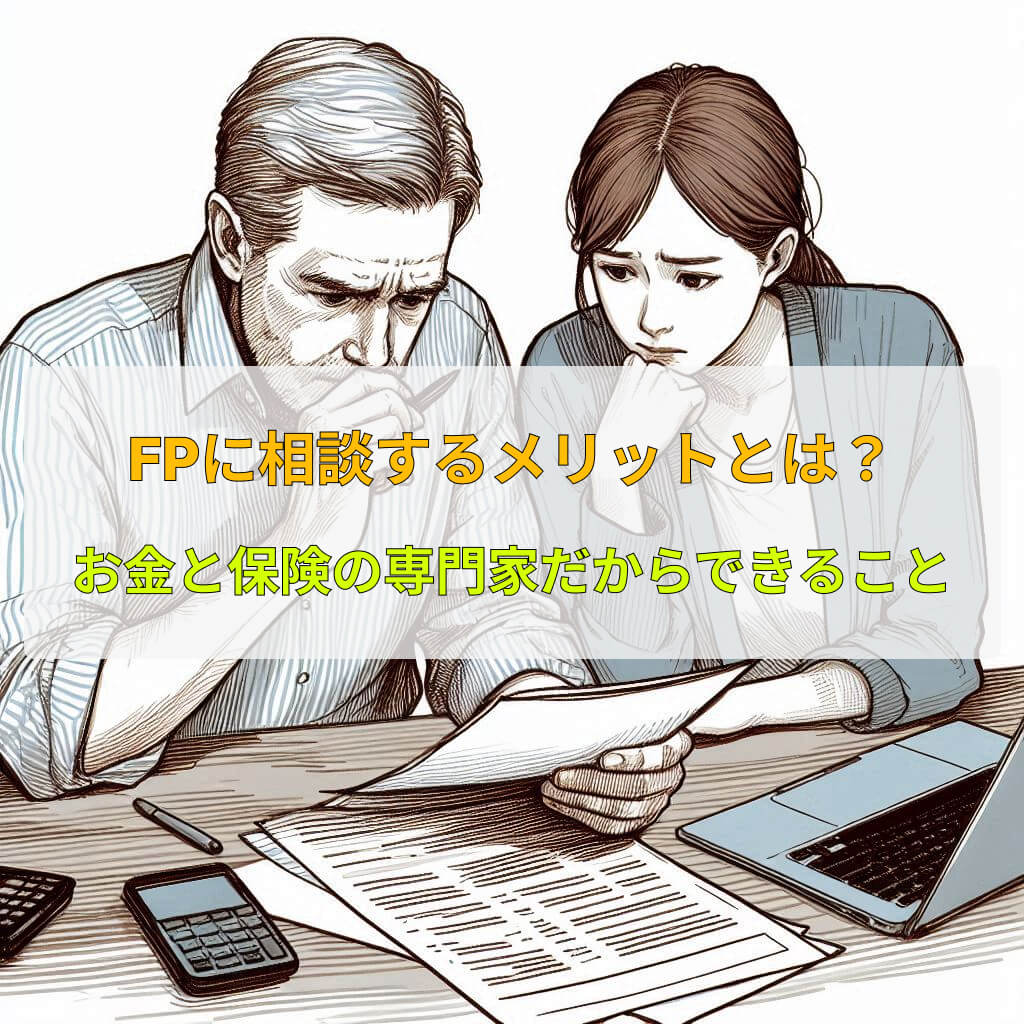医療費の負担を軽くしたいと考える方にとって、セルフメディケーション税制と医療費控除は効果的な節税手段です。
しかし、2つの制度には厳密な決まりがあるため、どちらを選択すべきか迷っている方も多いかもしれません。
本記事では、セルフメディケーション税制と医療費控除をどう活用すれば最も効果的に節税できるのか、具体的な方法をわかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- セルフメディケーション税制と医療費控除の基本的な違い
- セルフメディケーション税制が適している人
- セルフメディケーション税制の活用例

この記事では、2つの制度の特徴と違いを学びましょう。
セルフメディケーション税制と医療費控除の基本的な違い
冒頭でもお伝えした通り、これらの2つの制度にはそれぞれに厳密な決まりがあります。
まずは、セルフメディケーション税制と医療費控除の基本的な違いについて見ていきましょう。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制は、健康維持や病気予防のために一定の医薬品を購入した際、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。
この制度は、健康の維持・増進を自己責任で行うことを促進し、医療費の負担軽減を目的としています。
セルフメディケーション税制の対象となるのは、市販薬(OTC薬)で、風邪薬、胃腸薬、アレルギー薬などが含まれ、医師の処方箋を必要としない薬に限定されます。
対象となる医薬品を購入した場合、過去1年以内に健康診断や予防接種を受けた証明書を提出することで、年間最大12,000円の控除を受けることができます。

OTC薬(Over-The-Counter薬)は、処方箋なしで購入できる市販薬のことを指します。
合わせて読みたいコラム
・セルフメディケーション税制の基本ガイド|対象となる医薬品とは?
医療費控除とは?
医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その一部を所得から控除して税金を軽減する制度です。
医療費控除の対象となるのは、以下のような費用です。
・診療費、治療費(病院や診療所での治療にかかる費用)
・薬代(医師に処方された薬や市販薬)
・入院費、手術費
・通院にかかる交通費(公共交通機関の料金など)
・医療機器、治療器具(医師の指示によるもの)
・歯科治療費(治療が医療行為として認められる場合)

医療費控除の金額は、以下の計算式で求めます。
①所得金額が200万円以上の場合
支払った医療費から10万円を引いた金額が、医療費控除の対象となります。
②所得金額が200万円未満の場合
支払った医療費の金額から10万円を引いた金額ではなく、所得金額の5%が控除対象となります。
ちなみに所得控除って?基本のおさらい
所得控除は、年間の所得金額から控除額を差し引き、課税対象となる所得を減らす仕組みです。
たとえば、年収500万円の人が医療費控除や生命保険料控除を受けると、500万円から控除額分が引かれ、税金が軽減されます。
控除を受けるには、通常、確定申告を行うか、年末調整を受ける必要があります。
例えば、医療費控除を受ける場合は、支出した医療費の領収書を集め、確定申告で申請します。

なお、所得控除には、次のような控除が適用されます。
所得控除の種類
・基礎控除
・配偶者控除
・扶養控除
・医療費控除
・寄附金控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除など
セルフメディケーション税制はどんな人に向いているの?
1年間でOTC医薬品の購入費が12,000円を超えた場合、セルフメディケーション税制を適用する条件の一つを満たすことになります。
それでは、セルフメディケーション税制がどのような人に向いているのか、具体的に見ていきましょう。
セルフメディケーション税制に向いている人の特徴
セルフメディケーション税制は、一定の条件を満たした医薬品の購入費が所得控除の対象となる制度です。
そのため、次の4つの条件を満たす人が利用しやすい制度です。
1. 医療費が年間10万円未満の人
通常の医療費控除は、年間10万円以上の医療費が必要ですが、セルフメディケーション税制は年間12,000円以上の対象医薬品を購入すれば適用されます。
そのため、医療費控除の対象とならない人でも利用できます。
2. 風邪薬や鎮痛剤などの市販薬をよく購入する人
対象となるのは、スイッチOTC医薬品です。
風邪薬・鎮痛剤・胃腸薬などを日常的に購入する人に適しています。
3. 健康診断や予防接種を受けている人
適用条件として、健康診断や予防接種などを受けていることが求められます。
そのため、健康診断や予防接種を定期的に受けている人にとっては、利用しやすい制度です。
4. 確定申告を行う人
セルフメディケーション税制を利用するには確定申告が必要です。
セルフメディケーション税制が適用されにくい人の特徴
セルフメディケーション税制が適用されにくい人には、以下の3つの特徴があります。
1. 医薬品の購入が少ない人
年間12,000円以上の対象医薬品を購入することが一つの条件です。
そのため、市販薬をほとんど購入しない人には、この税制を利用しにくくなります。
2. 健康診断や予防接種を受けていない人
健康診断や予防接種を受けていることが条件です。
これらを受けていない場合、税制を適用することはできません。
3. 医療費が年間10万円以上の人
通常の医療費控除を利用している人は、すでに年間10万円以上の支出があるため、セルフメディケーション税制を別途利用することはできません。

再度繰り返しの内容になってしまいましたが、セルフメディケーション税制には厳格な決まりがあるので、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
セルフメディケーション税制の3つのポイント
①年間12,000円以上の対象医薬品の購入が必要
②健康診断や予防接種の受診が必要
③確定申告が必要
セルフメディケーション税制を活用した節税方法
最後に、セルフメディケーション税制を活用して税金を節約する方法について見ていきましょう。
この制度を実際に活用することで、どの程度の節税が可能なのか、実例を交えながらご紹介します。
医療費控除とセルフメディケーション税制を活用した使用例
実際に活用する際のイメージを具体化するために、2つの制度をそれぞれ使用した場合のシミュレーションをご紹介します。
仮定条件:年収400万円、課税所得が195万円以下の場合の医療費控除の比較
Ⓐ従来の医療費控除を利用した場合
医療費総額: 125,000円
控除額: 25,000円(125,000円 - 100,000円)
所得税: 25,000円 × 5% = 1,250円
住民税: 25,000円 × 5% = 1,250円
合計金額: 1,250円 + 1,250円 = 2,500円
Ⓑセルフメディケーション税制を利用した場合
医薬品代金: 30,000円
控除額: 18,000円(30,000円 - 12,000円)
所得税: 18,000円 × 5% = 900円
住民税: 18,000円 × 5% = 900円
合計金額: 900円 + 900円 = 1,800円

自身の具体的な数字を知りたい場合は、以下シミュレーションサイトを活用してみましょう。
セルフメディケーション税制のシュミレーションができるサイト
・日本一般用医薬品連合会『セルフメディケーション税制を活用した減税の一例』
FPに相談するメリットって?
FPにセルフメディケーション税制を相談することには、以下3つのメリットがあります。
①最適な活用方法の提案
FPは、相談者の年収や医療費の状況に応じて、セルフメディケーション税制の最適な活用法をアドバイスしてくれます。
②他の控除との併用アドバイス
他の控除や節税手段と併用する方法についても提案を受けることで、より効果的に税金を節約できる可能性があります。
③専門的な視点での疑問解決
セルフメディケーション税制だけでなく、他の公的制度や家計に役立つ情報を提供してもらえるため、疑問が解消され、安心して活用できます。

FPに相談することで、家計の経済的負担を見直すことができますよ!
FPに相談できるサイト
・FP無料相談の保険チャンネル
まとめ
今回の記事のまとめです。
医療費の負担を軽減するためには、『セルフメディケーション税制』と『医療費控除』が有効な節税手段です。
セルフメディケーション税制は、一定の対象医薬品を購入することで適用され、医療費控除は年間10万円以上の医療費がかかった場合に利用できます。
ただし、どちらの制度にも適用条件があるため、状況に応じた選択が求められます。