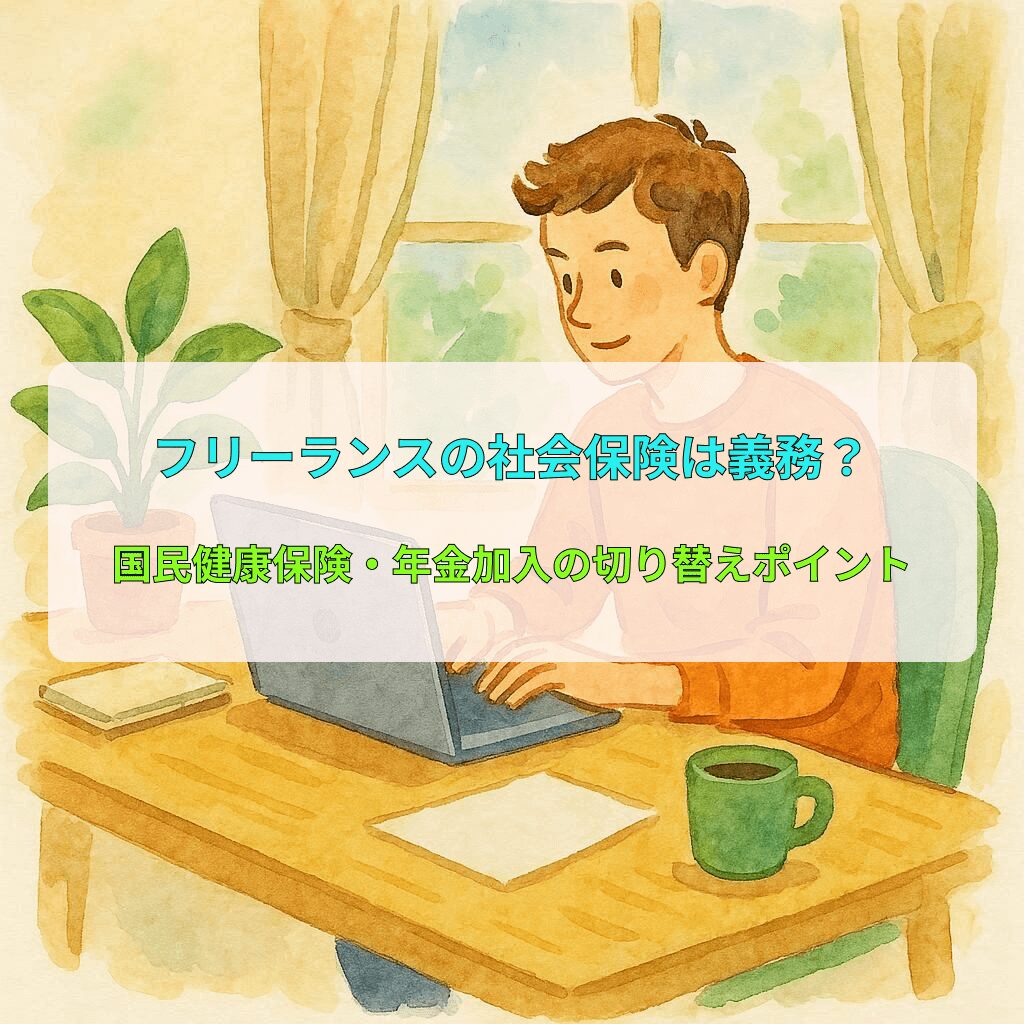働き方が多様化する現代では、社会保障制度の利用方法も、働き方に応じて変わってきます。
たとえば、会社員の場合は、企業が提供する社会保険に加入しており、健康保険や年金などの保障が手厚いのが特徴です。
一方で、個人事業主やフリーランスとして働く人は、自身で社会保険に加入する必要があるため、選べる制度が限られたり、保険料の負担が大きくなったりすることがあります。
そこで今回は、フリーランスとして働く方向けに、知っておきたい社会保険制度の基本と活用のポイントを、わかりやすくご紹介します。
この記事で分かること
- 会社員とフリーランスの社会保険制度の違い
- フリーランスが利用できる主な社会保険制度
- 社会保険制度をお得に活用する方法

フリーランスは、会社員と比べて社会保険にどんな違いがあるのか、一緒に見ていきましょう。
フリーランスが知っておくべき社会保険制度とは

フリーランスは会社員と比較して、利用できる社会保障が少ないという特徴があります。

まず初めに、フリーランスが知っておくべき社会保険制度について見ていきましょう。
保険の見直しで悩んでいるなら
・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!
フリーランスに必要な保険制度の種類
まずは、フリーランスの社会保険制度について知っておきましょう。
会社員とフリーランスの違いを明確にするため、以下に3つの特徴を整理してみます。

保険料負担の違いに注目して見てみましょう!
1. 健康保険
会社員
勤務先の健康保険に加入し、医療費の一部が保険で補われ、保険料は会社と従業員が折半します。
フリーランス
国民健康保険に加入し、保険料は全額自己負担します。
2. 年金保険
会社員
勤務先を通じて厚生年金保険に加入し、保険料は給与に応じて会社と従業員が折半します。
フリーランス
国民年金に加入し、保険料を全額自己負担します。
3. 労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険)
会社員
会社を通じて雇用保険に加入し、保険料は従業員も一部負担しますが、会社側の負担額の方が多くなります。
フリーランス
フリーランスは雇用保険に加入できないため、失業や労働災害に対する保障は自己管理する必要があります。
フリーランスが社会保険を活用するメリット
社会保険制度を利用する一番の目的は、日常のリスクに備えることです。
フリーランスとして自身で活動するということには、さまざまなリスクが潜んでいます。
例えば、自身のけがや病気、扶養家族の生活援助などが挙げられます。
こうしたリスクに対処するためにも、国民健康保険や国民年金などの社会保険制度に加入することが重要です。
これにより、医療費の負担軽減や老後の年金、さらには障害や死亡時の保障を得ることができます。

公的制度に関する詳細は、以下のコラムも参考にしてみてください。
関連コラム
・配偶者控除×扶養控除は併用可能?具体例から学ぶ2つの控除対象の違い
社会保険の加入は義務?国保と国民年金への加入
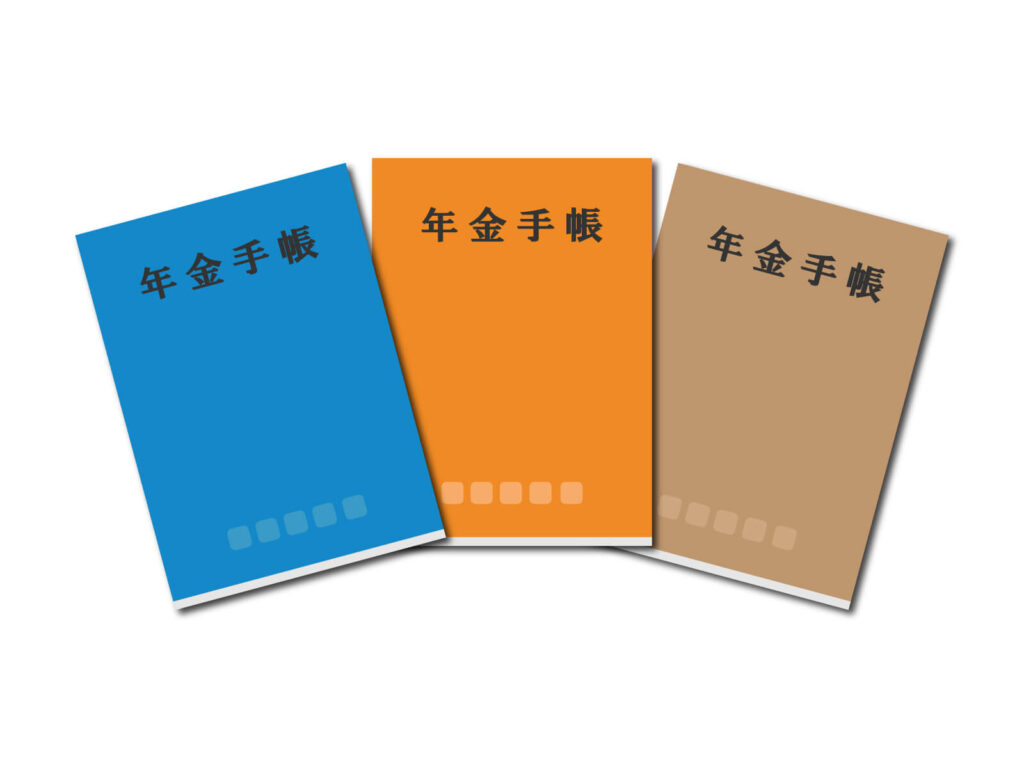
先ほどもお伝えしましたが、フリーランスとして働く場合、国民健康保険と国民年金に加入することが必要です。

この章では、フリーランスが知っておくべき2つの公的制度、国民健康保険と国民年金について詳しく解説します。
国民健康健康保険への切り替え
会社員だった方の場合、フリーランスで活動を始める前には、国民健康保険への切り替えが必要です。
国民健康保険は、国の公的な医療保険制度であり、加入者が病気やけがの治療を受ける際の医療費の自己負担額は原則として3割です。
保険料は前年度の所得、世帯人数、加入者の年齢を基に算出され、全額自己負担となります。
国民健康保険のワンポイント
国民健康保険では扶養制度がなく、傷病手当金等は原則として受け取れない。

なお、会社を辞めてフリーランスになった人も、条件を満たせば健康保険の任意継続制度に加入できます。
関連コラム
・退職後の健康保険任意継続を選ぶメリットとは
厚生年金と国民年金の違い
会社員を辞めてフリーランスになる場合、原則として国民年金のみの加入となります。
厚生年金は国民年金の「二階建て」部分にあたるため、フリーランスとして活動する場合には加入できません。
つまり、厚生年金は、企業に雇われている場合に限り加入できるため、フリーランスとして独立すると、国民年金のみに切り替わることになります。
国民年金のワンポイント
フリーランスや個人事業主を含む20〜59歳のすべての人は、国民年金への加入と保険料の支払いが義務付けられている。

国民年金では、保険料が全額自己負担であり、2025年度の月額保険料は17,510円に設定されています。
参照サイト
・日本年金機構『1.国民年金保険料の金額』
社会保険制度をお得に活用する方法とは?

では最後に、社会保険制度をお得に活用する方法について見ていきましょう。

フリーランス活動初期は所得が上がらないことが多いため、手取りを増やす2つの方法をご紹介します。
保障範囲と免除期間の把握
社会保険制度を正しく理解することは、将来の保障や保険料の負担を効率的に管理する上で大切です。
たとえば、高額療養費制度では、医療費が一定額を超えた場合に自己負担が軽減されます。
そのため、自分の月額負担の上限を把握しておくことで、民間の生命保険や医療保険でどの程度の保障が必要かを判断しやすくなります。
同様に、国民健康保険の保険料軽減制度や国民年金の免除・猶予制度を確認することで、経済的な負担を抑えつつ、必要な保障を確保することができます。

高額療養費制度については、以下のコラムでも詳しく解説しています。
関連コラム
・高額療養費制度の実例解説:自己負担限度額の適用をシミュレーションで学ぶ
・【年齢別】高額療養費制度の自己負担限度額|70歳を境にどう変わる?
税制上の優遇措置の活用
フリーランスが社会保険制度をお得に活用する方法の一つが、税制上の優遇措置を活用することです。
税制上の優遇措置を利用することで、社会保険料の負担を軽減することができます。
例えば、青色申告や小規模企業共済の利用など、税金の控除を受けることで、経済的なメリットを得ることができます。

ふるさと納税や定額減税など、フリーランスにとってお得な制度を積極的に活用しましょう。
関連コラム
・個人事業主向け!ふるさと納税の節税メリットと注目自治体の特徴解説
・定額減税はいつまで?補足給付金と年収103万円超え時の対処法も併せて解説
まとめ
今回記事のまとめです。
フリーランスが知っておくべき社会保険制度には、国民健康保険と国民年金があります。
これらの制度は、病気やけが、老後の資金準備など、将来のリスクに備えるために大切ですが、
フリーランスは国民健康保険料を全額自己負担する必要があり、経済的な負担が大きくなります。
資料参考サイト
・厚生労働省:国民健康保険制度
・日本年金機構