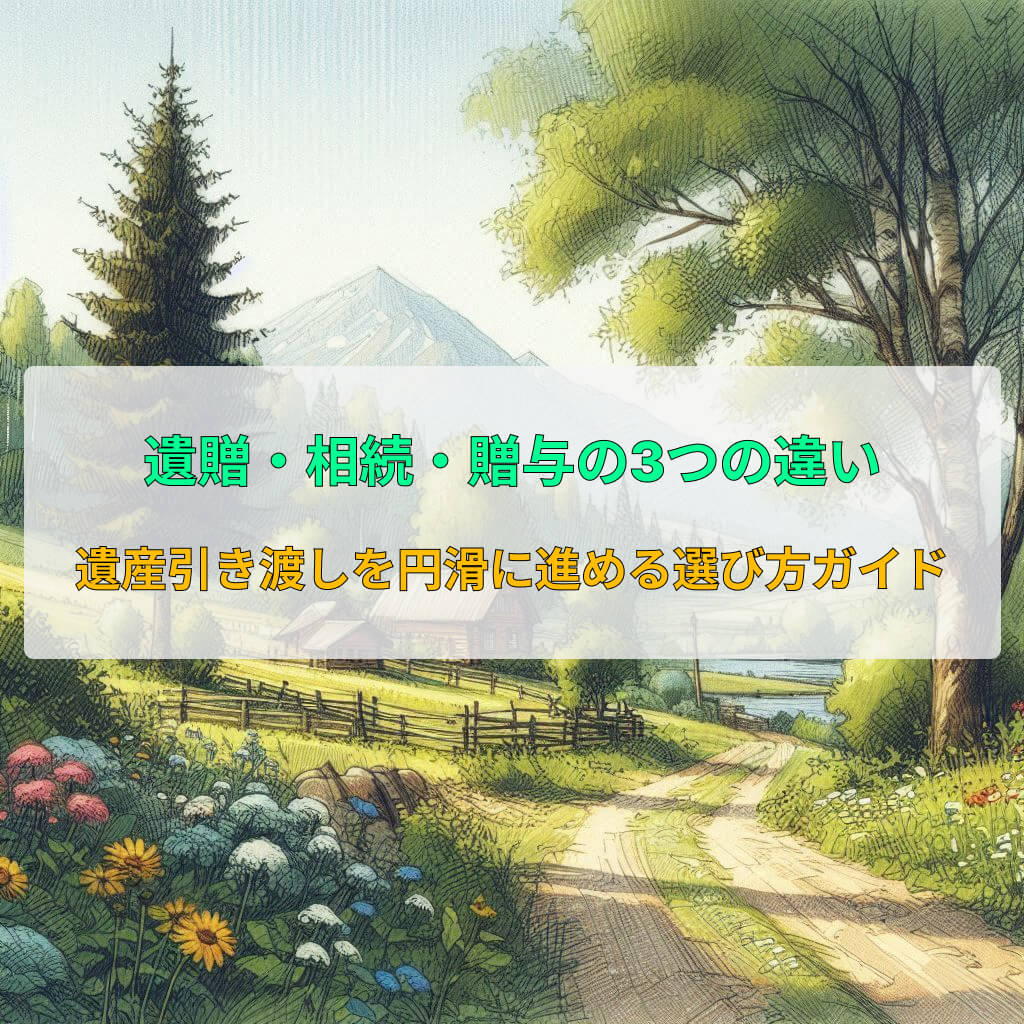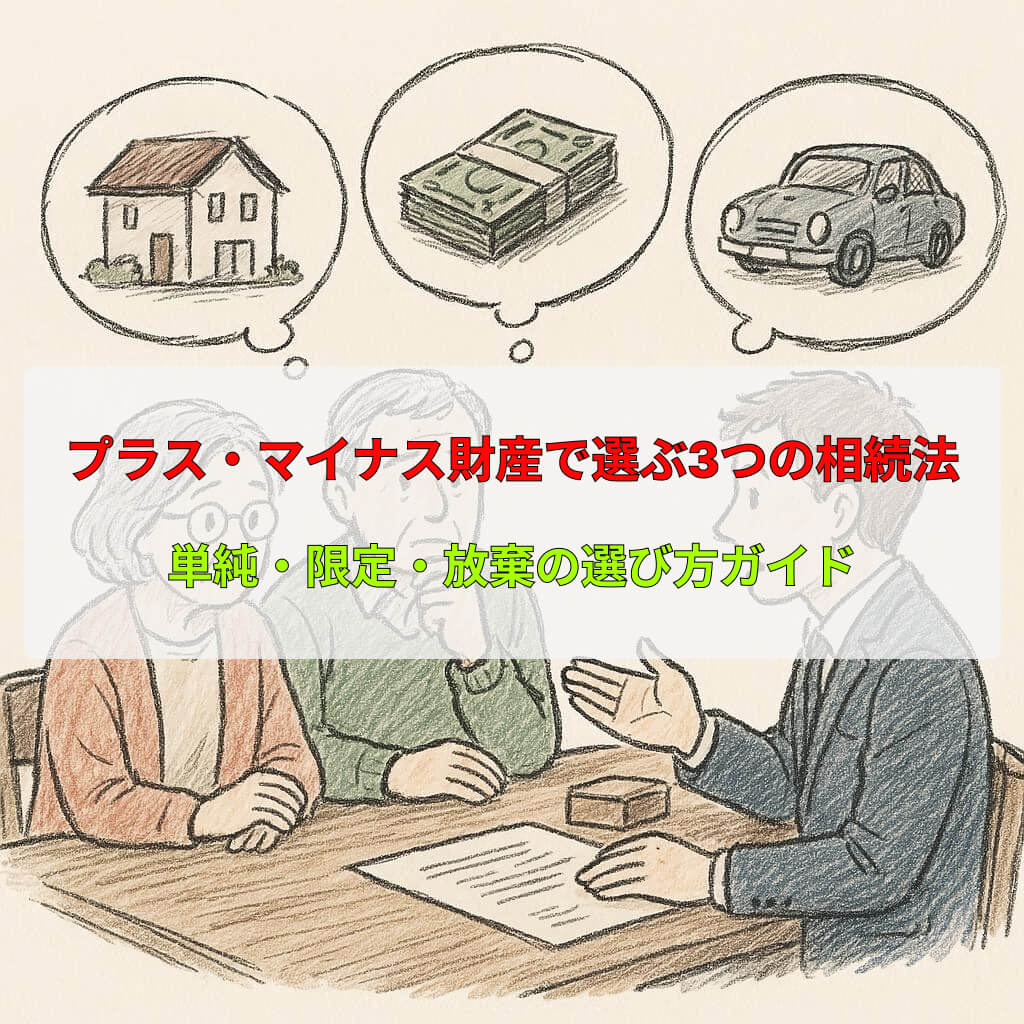財産を引き渡す方法には、「相続」「贈与」「遺贈」の3つの主要な選択肢があります。
ただし、それぞれの方法には、財産移転に伴う税金や手続きの違いがあり、選ぶ方法によって受け取る側に与える影響も大きく異なります。
この記事では、これら3つの方法の特徴と、それぞれを選ぶ際に注意すべき点について詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 遺産分割の3つの方法とその特徴
- 遺産分割で注意すべきポイント
- 遺産を円滑に引き継ぐための判断基準

「相続・贈与・遺贈」という3つの財産移転の方法によって、税金がどのように異なるのかを整理していきましょう。
遺産を引き渡す3つの方法とは?

相続・贈与・遺贈――言葉は聞いたことがあっても、適用される税金の違いまではイメージしづらいですよね。

まずは、遺産に関する3つの財産移転方法の特徴を見ていきましょう。
相続:法定相続人が財産を自動的に引き継ぐ
相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を、配偶者や子供などの法定相続人が引き継ぐ制度です。
相続には法的手続きが必要で、遺産分割協議が行われることもあります。
財産を受け継ぐ相手は、法律で定められた相続人に限られるため、誰が相続するのかが重要なポイントです。
また、相続に伴い相続税がかかり、受け取る遺産の評価額を基に税額が算出されます。
贈与:双方の合意で財産を譲渡
贈与とは、双方の合意のもとで財産を譲る行為です。
贈与を受けた人は、その財産に対して贈与税を支払う義務があり、贈与税は受け取った財産の評価額に基づいて算出されます。
また、贈与には、贈与者が生存中に行う「生前贈与」と、亡くなった後に効力を生じる「死因贈与」の2種類があり、贈与契約書の作成を求められる場合があります。

ただし、生前贈与と死因贈与では、課せられる税金の種類が異なるため、注意が必要です。
チェックポイント
・生前贈与→贈与税
・死因贈与→相続税
遺贈:遺言書に基づき財産を移転
遺贈とは、亡くなった方(被相続人)の財産を遺言によって他の人や団体に無償で譲る行為を指します。
遺贈は遺言書に基づき行われ、相続とは異なり、遺贈は法定相続人以外の人物や団体にも財産を譲ることができる点が特徴です。
遺贈を受けた人には相続税が課せられ、税額は受け取った財産の評価額に基づいて算出されます。
遺贈には、以下の2種類があります。
特定遺贈:特定の財産を指定して譲るもの。
包括遺贈:遺産全体の一部や割合を譲るもの。

遺贈については、以下のコラムでも詳しく解説しています。
参照コラム
・遺贈で譲渡できる財産とは?仕組みと注意点を解説
遺産の引き渡しを円滑に進めるために知っておくべきこと
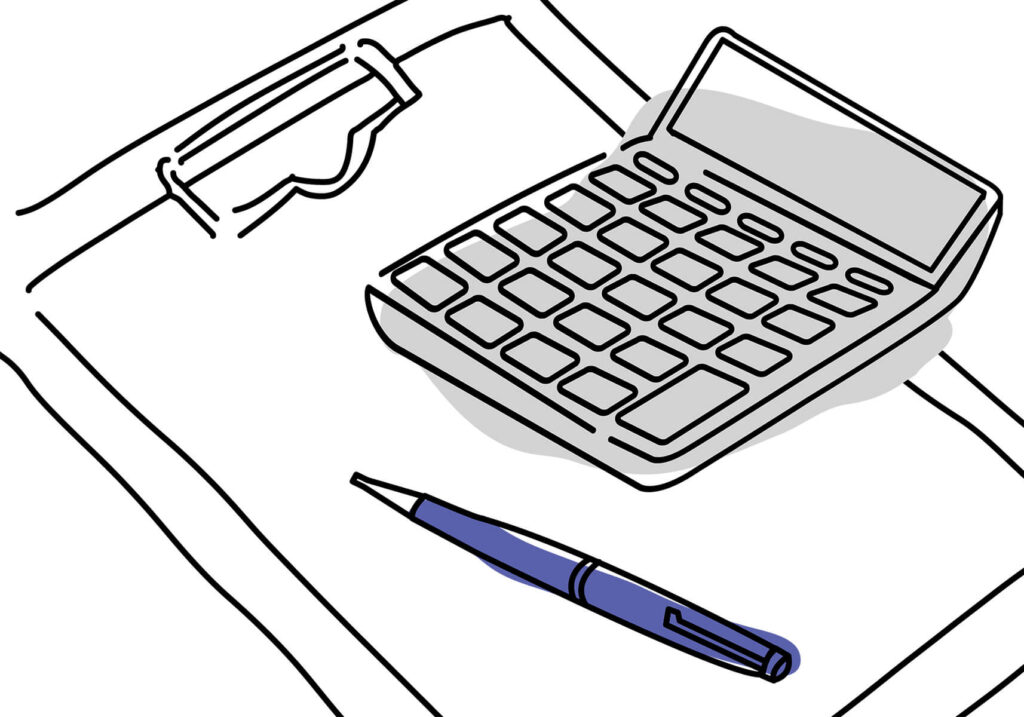
遺産移転には原則として税金が課されるため、相続税や贈与税について正しく理解しておくことが大切です。

この章では、遺産の引き渡しを円滑に進めるための4つのポイントを見ていきましょう。
1.遺産分割協議書の役割
遺産分割協議書は、相続人が故人の遺産をどのように分けるかを取り決めるための書類です。
これを作成しておくことで、相続手続きを円滑に進められるほか、遺産分割に関する争いを防ぐための法的効力を持たせることができます。

ただし、遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の署名と捺印が必要です。
参照コラム
・遺産分割協議書の必要性とは?作成しない場合に起こる4つの相続リスク
2.相続による遺産の引き渡し期限
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
限定承認や相続放棄を選択する場合は、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
そのため、期限を過ぎると、自動的に単純承認とみなされ、財産だけでなく債務もすべて相続することになります。

3つの相続方法の違いについては、以下のコラムをご参照ください。
参照コラム
・プラス・マイナス財産で選ぶ3つの相続法|単純・限定・放棄の選び方ガイド
3.相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続開始日(故人の死亡日)から10か月以内です。
そのため、期限内に相続税の申告書を作成し、納税資金の準備も進める必要があります。
なお、相続税は現金一括納付が原則ですが、延納や物納の利用を検討することもできます。

延納は、相続税を分割して支払う方法で、
物納は、現金の代わりに相続財産で納める方法です。
参照サイト
・国税庁『延納・物納申請等』
4.贈与税の申告期限
贈与税の申告が必要となるのは、年間110万円を超える贈与を受けた場合です。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
そのため、期限内に申告を行わないと、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。

詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
参照サイト
・国税庁『No.4429 贈与税の申告と納税』
どの方法を選ぶべき?遺産引き渡し時の判断ポイント

遺産を移転する際には、原則として税金がかかることは理解いただけたかと思います。
ここでポイントとなるのは、どの方法を選ぶかによって税金や手続き、受け取る側の影響が大きく変わるという点です。

最後に、遺産移転時の3つの選択基準を確認していきましょう。
法的・税務的な観点から見る選択基準
改めて、これまで解説してきた3つの財産の引き渡し方法について、選択時のポイントを整理してみましょう。
相続
・被相続人の死亡後に財産が移転。
・法定相続分に従うか、遺産分割協議で決定。
・原則として相続人が自動的に取得(単純承認)。
贈与
・生前に財産を移転することが可能。
・受贈者を自由に選択することが可能(相続人以外にも可能)。
・一定額(年間110万円)を超えると贈与税が課税。
遺贈
・被相続人の死亡後に財産が移転。
・遺言書に基づき財産を移転。
・法定相続人以外にも財産を残すことが可能。

当サイトでは、他にも相続に役立つコラムを綴っているので、ぜひ併せてご参照ください。
あわせて読みたいコラム
・相続土地国庫帰属制度の審査手数料ってどのくらい?申請時の詳細ガイド
まとめ
今回の記事のまとめです。
財産を引き渡す方法には、相続・贈与・遺贈の3つがあります。
それぞれの方法によって課税額が異なるため、事前に適切な知識を身につけておくことが大切です