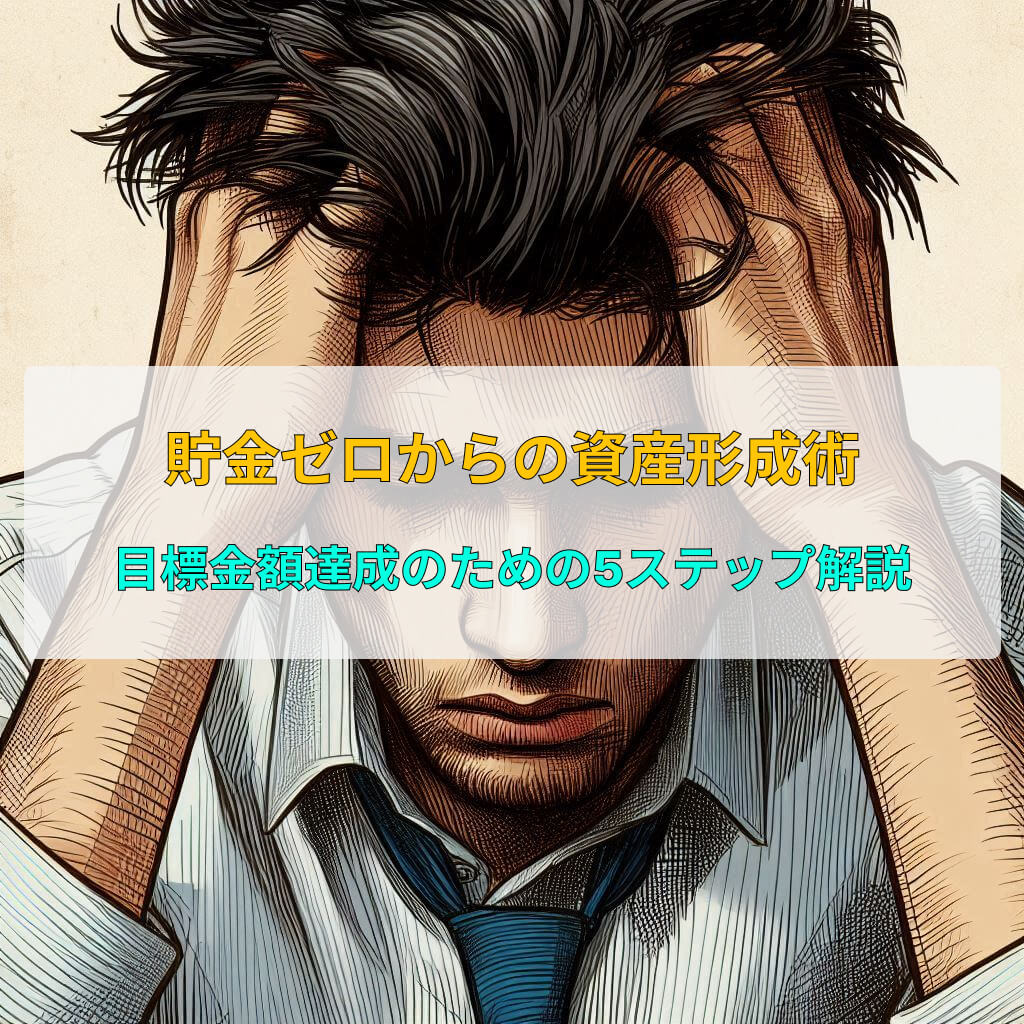『貯金をしたいけど、いい方法はないの?』
お金を貯めることは、生活の安定や将来に備えるために欠かせない要素ですが、忙しい日々の中で貯金を続けるのはなかなか難しいものです。
そんな中で、財形貯蓄制度は、給与天引きという手軽な方法で、無理なく貯金を習慣化できる仕組みです。
この記事では、財形貯蓄制度の魅力や活用法、さらに注意点について詳しくご紹介します。
この記事で分かること
- 財形貯蓄制度の概要
- 財形貯蓄制度を利用するメリット・デメリット
- 財形貯蓄制度を最大限に活用する方法

この制度を活用することで、会社員にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
財形貯蓄制度とは?基本的な仕組みを理解しよう

「貯金」という言葉には馴染みがある一方で、「貯蓄」と聞くと少し堅苦しく感じることもありますよね。

まず初めに、財形貯蓄制度の概要について見ていきましょう。
財形貯蓄制度の概要
財形貯蓄制度は、正式には「勤労者財産形成貯蓄制度」と呼ばれ、従業員が給与天引きで自動的に貯蓄を行える仕組みです。
企業がこの制度を福利厚生として導入している場合、その企業の従業員が利用できます。

財形貯蓄制度の基本的な特徴は、以下の3点です。
①給与天引きで自動的に積立
毎月の給与から決まった金額が自動的に天引きされるため、意識せずに無理なく貯蓄を続けられます。
➁利用対象者
福利厚生として導入している企業に勤務する従業員のみが利用でき、個人での直接利用はできません。
③利子に対する税制優遇
元利合計550万円まで非課税となり、通常の預貯金利子にかかる約20%の税金が免除されるメリットがあります。
参照元サイト
・厚生労働省『財形貯蓄制度』
・No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁
財形貯蓄の種類とその違い
財形貯蓄には、主に3つの種類があり、それぞれ目的や利用条件が異なります。

以下に、3つの特徴の違いをそれぞれ説明します。
1. 一般財形貯蓄
目的
生活資金や急な支出に備える貯蓄として利用できます。
契約要件
年齢制限はなく、誰でも利用可能です。
積立て期間
原則3年以上、定期的に積み立てる必要があります。
積立ての中断
いつでも自由に積立を中断できます。
引き出し制限
貯蓄開始から1年以上経過すれば、積立金を自由に引き出すことができます。
金融機関の変更
3年以上保有している場合は、金融機関を変更することができます。
参照サイト
・勤労者財産形成事業本部『一般財形貯蓄について』
2. 財形年金貯蓄
目的
年金として受け取ることを目的とし、老後の生活費を準備するための貯蓄です。
契約要件
55歳未満の方が対象で、55歳を超えると新たに契約できません。
積立て期間
積立期間は5年以上です。
積立ての中断
積立の中断が2年以上続いた場合、利子が課税対象になります。
引き出し制限
年金目的以外で解約や引き出しを行うと、過去5年間の利子に課税されます。
金融機関の変更
保有期間に関わらず、金融機関の変更はできません。
参照サイト
・勤労者財産形成事業本部『財形年金貯蓄について』
3. 財形住宅貯蓄
目的
住宅の取得や増改築を目的とした貯蓄で、自宅購入やリフォーム資金に利用されます。
契約要件
55歳未満の方が対象で、55歳を超えると新規契約はできません。
積立て期間
積立期間は5年以上です。
積立ての中断
積立の中断が2年以上続いた場合、利子が課税対象になります。
引き出し制限
住宅資金以外の目的で解約や引き出しをすると、過去5年間の利子が課税対象となります。
金融機関の変更
保有期間に関わらず、金融機関の変更はできません。
参照サイト
・勤労者財産形成事業本部『財形住宅貯蓄について』
財形貯蓄制度を利用するメリットとは?

財形貯蓄制度を活用する、メリットとデメリットは何でしょうか。
貯金を習慣化でき、必要なときに自由に引き出せる点がメリットですが、利用期間や引き出し制限など注意すべき点もあります。

この章では、財形貯蓄制度のメリット・デメリットについて解説します。
メリット①自動積立で貯金が習慣化できる
財形貯蓄制度のメリットの一つは、自動積立によって貯金が習慣化できることです。
具体的には、給与天引きで毎月一定額が自動的に貯蓄口座に積み立てられます。

貯金を習慣化することによるメリットには、次の3つがあります。
①意識的に貯金をする手間が省ける
給与から自動的に引き落とされる仕組みのため、無理なく貯金を続けられます。
➁給与引き落としのタイミングで貯金ができる
給与から先に天引きされることで、使いすぎを防ぎ、貯金が習慣化されます。
③意識的な貯金のモチベーションが続きやすい
自動的に積み立てられる仕組みにより、計画的に貯金を続けやすくなります。
メリット②目的に応じた資金を確保しやすい
財形貯蓄制度では、一般財形、年金財形、住宅財形といった目的別の貯蓄方法があり、それぞれの用途に合わせて計画的に資金を準備できます。
これにより、ライフプランに沿った効率的な資金管理が可能になります。

資金を計画的に確保することで、ライフプランにおいて以下3つのメリットがあります。
①急な出費に対応しやすい
予期せぬ医療費や修理費など、急な出費にも対応しやすくなります。
②ライフイベントに柔軟に備えられる
結婚や出産、教育資金など、ライフステージの変化に応じて資金を活用できます。
③精神的な安心感が得られる
必要なときに資金を使えるため、経済的な不安を軽減できます。
デメリット①利用可能な期間や引き出し制限がある
一方で、財形貯蓄のデメリットについても理解しておく必要があります。
主なデメリットは、利用可能な期間や引き出し制限があることです。
たとえ貯蓄目的が自由な一般財形貯蓄であっても、原則として積み立て開始から1年以上経過しないと引き出せないなどの制約があり、計画的な資金管理が求められます。
また、財形貯蓄制度は貯蓄の目的に応じて利用期間が定められているため、基本的には目的を達成するまで引き出せず、急な資金需要に対応しづらい場合があります。

これらの制約により、必要なときに自由に資金を引き出せない場合があることを押さえておきましょう。
デメリット②低金利で増えにくい貯金額
財形貯蓄のもう一つのデメリットは、金利が低いため貯金が増えにくい点です。
一般的に、財形貯蓄の金利は銀行の定期預金や普通預金より低く設定されているため、長期間積み立てても資産の増加が限定的になることがあります。
そのため、資産形成を目的とする場合は、他の投資商品や貯蓄方法と併用して計画的に運用することも検討が必要です。

財形貯蓄はあくまで貯蓄を目的としており、元本保証があるため、リスクを避けながら安定的な貯蓄を目指すものです。
あわせて読みたいコラム
・新NISAから始める資産運用!SBI証券での口座開設ステップ解説
財形貯蓄制度を最大限に活用する方法
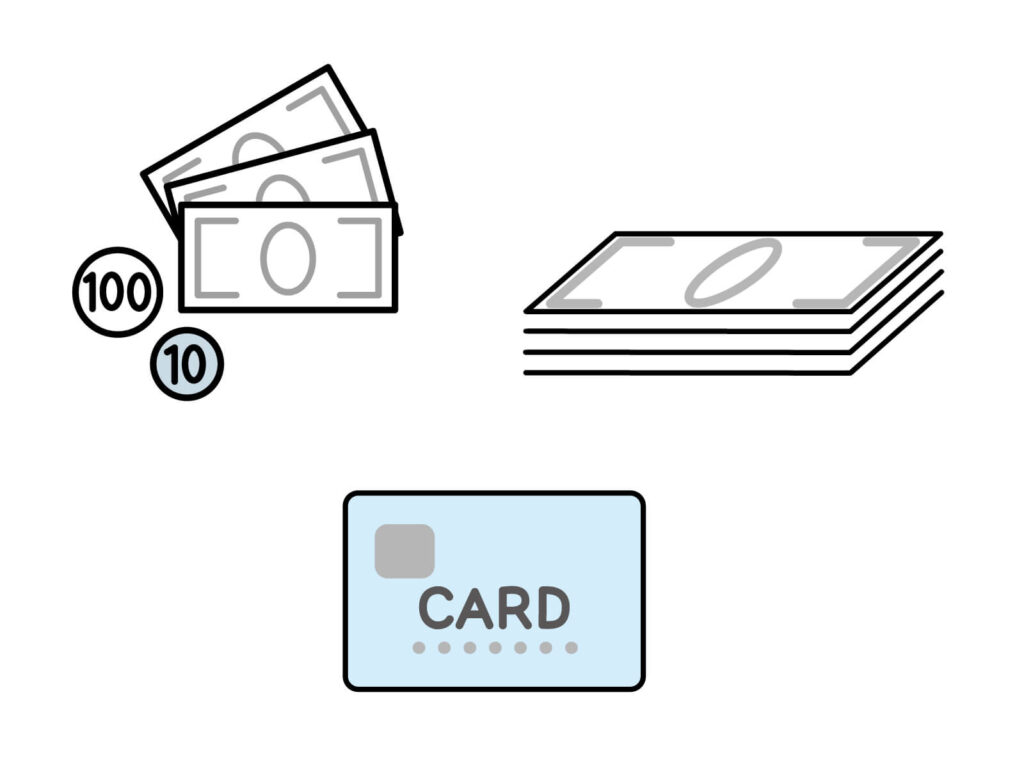
お伝えしてきた通り、財形貯蓄制度の3つのタイプは、それぞれ目的に応じた貯蓄方法が定められています。
では、この財形貯蓄制度を最大限に活用するにはどうすればよいのでしょうか。

最後に、貯蓄目標を明確に設定することの重要性について見ていきましょう。
貯蓄目標に応じた運用方法の選択
貯蓄の目標を明確にすることで、資産を効率的に運用し、必要なタイミングで適切に資金を引き出せるようになります。

具体的には、以下2つのポイントを押さえておきましょう。
①貯蓄目標に応じた運用方法の選択
貯蓄の目的が明確であれば、その目標に応じた運用方法を検討できます。
たとえば、短期的な目標(旅行資金や急な支出に備える貯金)には比較的リスクの低い定期預金や財形貯蓄が選ばれることが多く、長期的な目標(老後資産形成や住宅購入)では投資信託や株式など、リスクを伴う運用も検討されます。
➁ 投資と貯金のバランスを考慮する
投資と貯金をバランスよく組み合わせることで、リスクを分散しながら安定した資産形成が可能になります。
貯金だけでは金利が低く資産を大きく増やしにくいため、長期的な資産形成には一定のリスクを取った投資も検討が必要です。
急な出費に備える資金は、普通預金や財形貯蓄など流動性の高い手段で確保し、長期的に増やしたい資産は投資に回すなど、目的に応じた使い分けが重要です。

貯蓄と運用は役割が異なるため、まずは目的を明確にし、その上で適した方法を選ぶことが大切です。
まとめ
今回の記事のまとめです。
財形貯蓄制度は、企業が導入する給与天引き型の貯蓄制度で、従業員のみが利用できます。
制度には、一般財形・財形年金・財形住宅の3種類があり、自動積立による貯蓄の習慣化や、利子が非課税になるといったメリットがあります。
一方で、引き出しに制限があることや、金利が低く資産が増えにくい点がデメリットです。