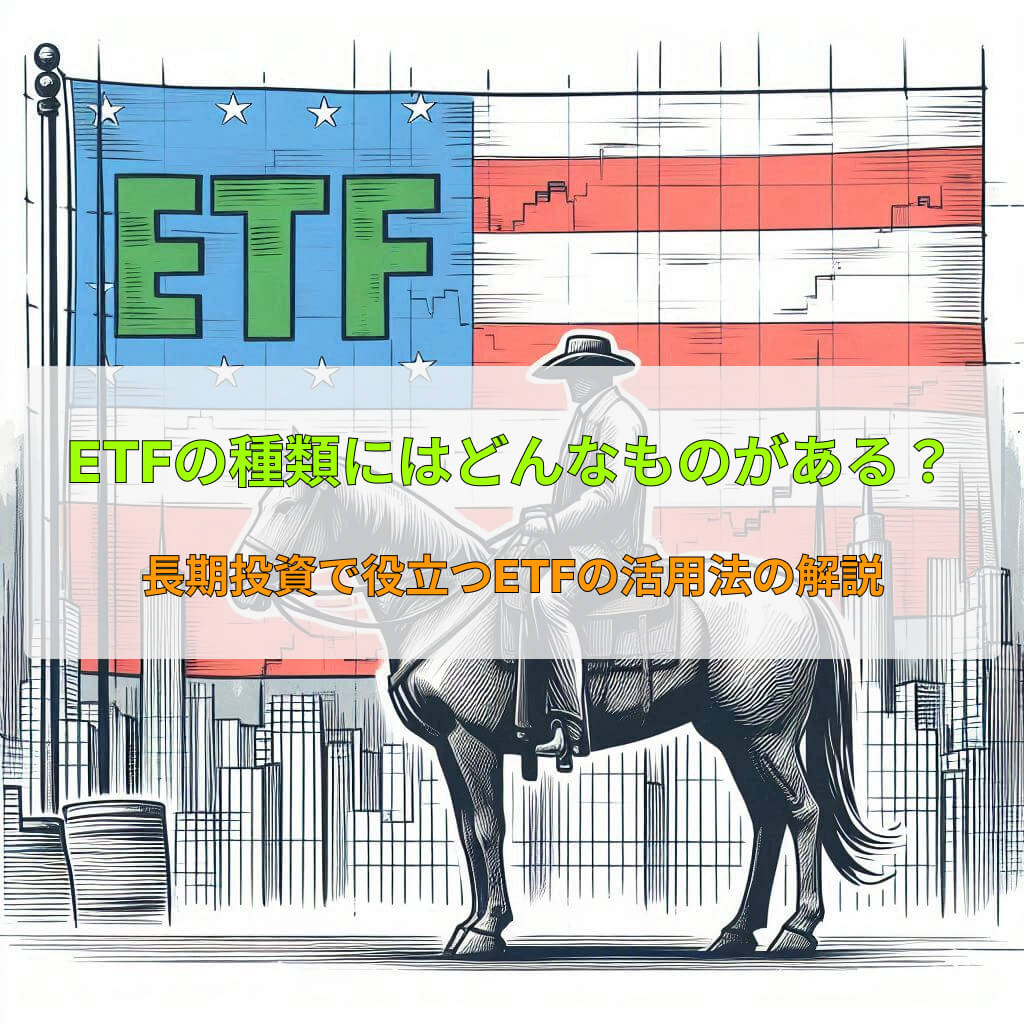ETF(上場投資信託)は、株式や債券、商品などに手軽に投資できる金融商品です。
そしてETFには、特定の指数に連動する「インデックス型」と、指数にとらわれずに運用される「アクティブ型」の2種類があります。
それぞれ異なる運用戦略があり、投資家は自身の目的や投資スタイルに合わせて選ぶことが重要です。
この記事では、ETFの種類と、ETF投資を始める際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
この記事で分かること
- ETF(上場投資信託)の基本的な特徴
- ETFの主な種類とそれぞれの運用戦略
- 投資目的に合わせたETFの選び方のポイント

ETFの具体的な種類や、ETF投資を始めるために知っておきたいポイントについて、一緒に学んでいきましょう。
ETFを使った投資戦略

そもそも、ETFとは、上場投資信託(Exchange Traded Fund)の略称で、株式のように証券取引所で売買できる投資信託の一種です。
株式や債券、商品など複数の資産をまとめて保有できるため、少額からでも手軽に分散投資ができるのが大きな特徴です。

まず初めに、ETFを活用した投資戦略について見ていきましょう。
長期投資におけるETFの活用法とは?
長期投資においてETFは、リスク分散と低コストの面で効果的な選択肢となります。

ETFを長期的な投資戦略に組み込むことには、主に次の4つのメリットがあります。
1. 分散投資の実現
ETFは、特定の株価指数や債券、商品などに連動するため、少額で広範囲な分散投資が可能です。
例えば、日経225やS&P500に連動するETFを通じて、数十社以上の企業に一度に投資することができます。
2. 低コストで投資
ETFは一般的に、アクティブファンドに比べて運用コストが低いとされています。
長期投資では、コストが積み重なることがリターンに影響を与えるため、低コストで運用できる点がメリットです。
3. 指数連動型の活用
インデックスETFは、市場全体や特定のセクター、地域に連動するため、特定の市場の成長を長期的に享受できる可能性があります。
例えば、S&P500に連動するETFを選ぶことで、米国株式市場の動向に連動した投資が可能になります。
4. 再投資による効果
ETFで得た配当金や利息を再投資することで、複利効果を得ることができます。
再投資を行うことで、長期的に資産を増やす助けとなります。
定期的な積立投資とETFの組み合わせとは?
定期的な積立投資とETFの組み合わせとは、ETFを毎月など決まったタイミングで一定額ずつ購入する方法です。
これにより、価格変動の影響を抑えながら、長期的に安定した資産形成を目指せます。

以下2つのポイントを押さえておきましょう。
1. 安定した成長の実現
ETFの多くはインデックス型で、市場全体の動きに連動する特徴があります。
そのため、市場の動向を反映したリターンが見込めます。
また、定期的に一定額を積み立てることで、市場の価格変動に影響されにくく、安定的に投資を続けることができます。
2. コスト効率の向上
ETFは一般的に信託報酬が低く、長期投資でコストを抑えやすい商品です。
さらに、定期的に積立投資を行うことで購入単価が平均化され、価格変動リスクを軽減しながら、投資にかかる総コストも抑えられます。

インデックス投資に関する詳細は、以下のコラムをご参照ください。
参照コラム
・インデックス投資の魅力|S&P500・日経平均に連動する投資法入門
ETFの種類とは?|インデックスETFとアクティブETF
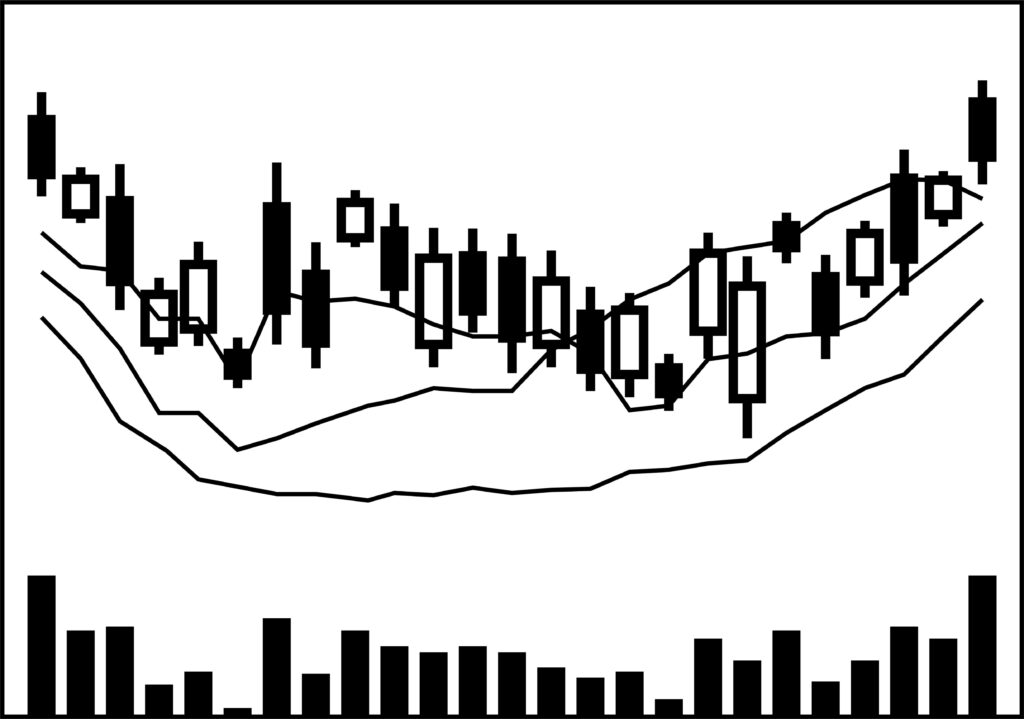
少し前置きが長くなりましたが、ここからはETFの種類について見ていきましょう。
冒頭でお伝えしたように、ETFにはインデックスETFとアクティブETFの2種類があります。

それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
インデックスETF
インデックスETFは、特定の市場指数(インデックス)に連動することを目的としたETFです。
例えば、日経225やS&P500などの株価指数に連動するETFがこれにあたります。
インデックスETFの5つの特徴
1. 運用目的
市場全体や特定のセクター・地域の指数に連動することを目指します。
2. 運用手法
指数に基づいて構成銘柄を同じ割合で保有し、指数と同じ動きを目指してトラッキングエラーを最小化するよう運用されます。
3. コスト
パッシブ運用で頻繁な売買がないため、一般的に運用コストが低く抑えられます。
4. メリット
低コストで市場全体や特定分野に分散投資でき、指数に連動するため予測や短期的な市場動向に左右されにくい特徴があります。
5. 代表例
・S&P500 ETF(米国株式市場全体に投資)
・日経225 ETF(日本の代表的な株価指数に投資)
アクティブETF
アクティブETFは、指数に連動せず、ファンドマネージャーが積極的に銘柄を選んでパフォーマンス向上を目指すETFです。
アクティブETFの5つの特徴
1. 運用目的
市場のパフォーマンスを上回るリターンを目指して、積極的に運用されます。
2. 運用手法
ファンドマネージャーが銘柄選定や売買タイミングを決め、市場平均とは異なる戦略で運用します。
3. コスト
アクティブ運用のため、インデックスETFより運用コストが高くなりやすく、頻繁な売買に伴う取引手数料や運用費用が増えることがあります。
4. メリット
市場平均を上回るリターンを狙える可能性があります。
5. 代表例
・テーマ型ETF(例:テクノロジー、ヘルスケア、ESGなど特定テーマに焦点を当てたETF)
・アクティブ運用を行う株式ETF
インデックスETFとアクティブETFの特徴のまとめ
先ほどご紹介した内容を踏まえて、インデックスETFとアクティブETFの特徴を以下の図1にまとめてみます。
| 特徴 | インデックスETF | アクティブETF |
|---|---|---|
| 運用方法 | 指数に連動したパッシブ運用 | ファンドマネージャーによるアクティブ運用 |
| 目的 | 市場の平均的なパフォーマンスを目指す | 市場を上回るリターンを目指す |
| コスト | 低い | 高い |
| リスク | 市場の平均的なリスクに連動 | ファンドマネージャーの運用能力に依存 |
| 利点 | 分散投資と低コストが可能 | 高いリターンを狙える可能性あり |
ETF投資を始めるために知っておくべきこと

ETF投資を始めるには、基本的なポイントを押さえることが大切です。

最後に、ETF投資を始める前に確認しておくべきポイントについて見ていきましょう。
投資リスクの把握
ETF投資を始める際は、投資リスクを十分に理解しておくことが重要です。

ここでは、ETF投資で注意すべき6つのリスクについて解説します。
1. 市場リスク(価格変動リスク)
ETFは株式や債券などの資産に投資しているため、対象となる市場や指数の動きに影響を受けます。
そのため、市場全体のトレンドや経済状況によっては、ETFの価格が大きく変動する可能性があります。
例えば、株式市場が下落すると、株式に連動するETFの価格も下がることがあります。
対策:
・長期的な視点での投資を考え、市場の短期的な変動に過剰に反応しないよう心掛ける。
・投資するETFの対象資産や市場について十分に理解する。
2. 流動性リスク
流動性リスクとは、希望する価格でETFを買ったり売ったりできないリスクです。
取引量が少ないETFは、スプレッド(売買価格の差)が広く、売買が難しくなる場合があります。
特に、ニッチな市場に連動するETFや小型ETFは流動性が低いことがあります。
対策:
・各ETFの取引量や流動性を確認してから投資する。
3. 金利リスク
金利の変動がETFの価格に影響を与える場合があります。
特に債券に連動するETFや不動産ETF(REIT)などは、金利の上昇によって価格が下がることがあります。
対策:
・短期債券や金利に敏感でない資産を組み合わせることで、金利上昇に対する影響を軽減する。
4. 追跡誤差リスク
ETFは特定の指数(インデックス)に連動することを目指していますが、実際には、その指数のパフォーマンスを完璧に追跡することが難しい場合があります。
これを「追跡誤差(トラッキングエラー)」と言います。
追跡誤差が大きいと、インデックスに対するパフォーマンスの乖離が生じ、期待したリターンが得られないことがあります。
対策:
・追跡誤差が小さいETFを選び、その運用方法や指数の追跡手法を確認する。
5. コストリスク(費用リスク)
ETFには管理費(信託報酬)や取引手数料があります。
これらのコストが長期的に積み重なると、最終的なリターンに影響を与えることがあります。
特に、信託報酬が高いETFは、長期投資でコストがリターンに大きな影響を及ぼすことがあります。
対策:
・信託報酬や取引手数料が低いETFを選択する。
6. 通貨リスク
海外のETFに投資する場合、為替リスクが発生します。
特に、米国株に連動するETFや外国債券に連動するETFは、円安や円高の影響を受けることがあり、投資リターンが増減する可能性があります。
対策:
・外貨建てのETFに投資する場合は、為替リスクを考慮する。
・為替ヘッジ付きのETFを選ぶ。

投資を行う際には、さまざまな要因を考慮する必要があります。
金利や為替リスクについても、正しい知識を身につけておきましょう。
資産運用について相談できるサイト
・資産運用の相談なら【オンアド】
まとめ
今回の記事のまとめです。
ETFにはインデックス型とアクティブ型の2種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
そのため、投資を始める前に各ETFの特徴をしっかり理解し、リスクを十分に把握することが大切です。