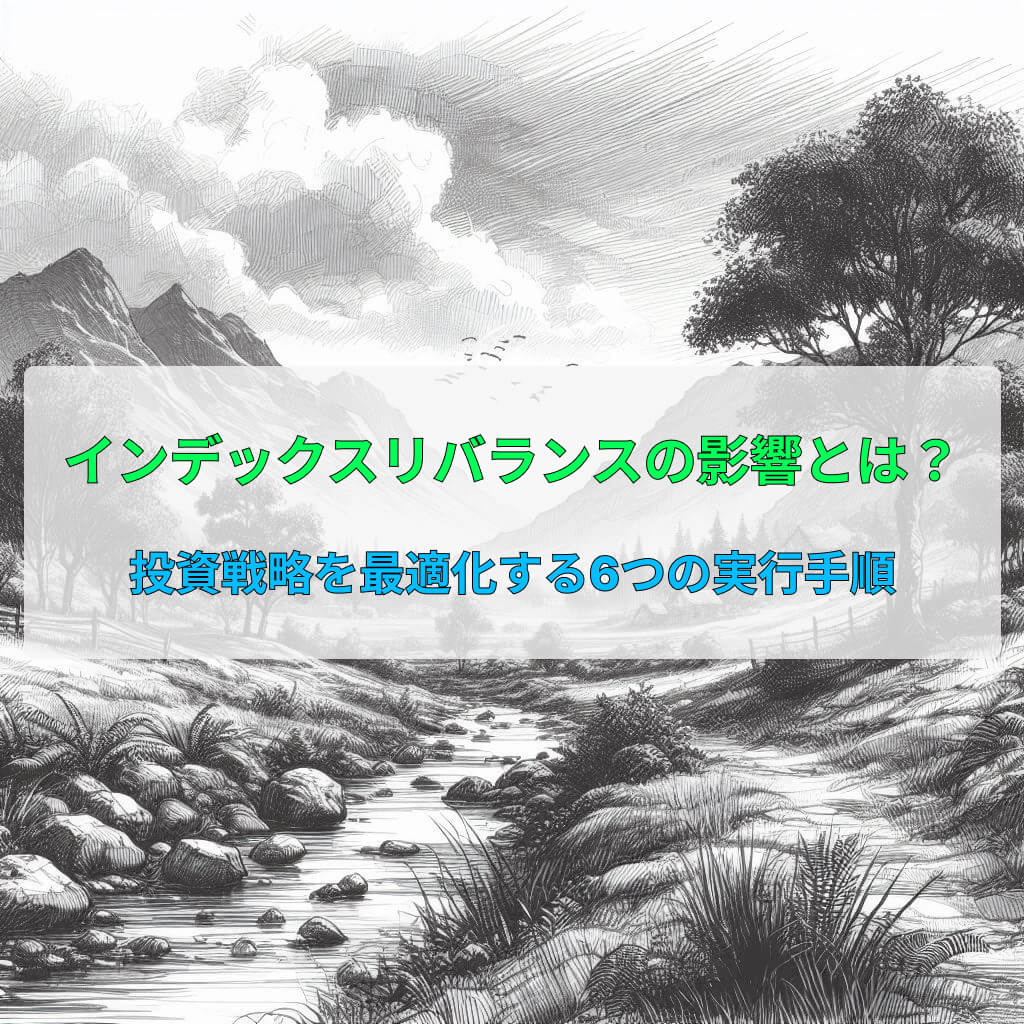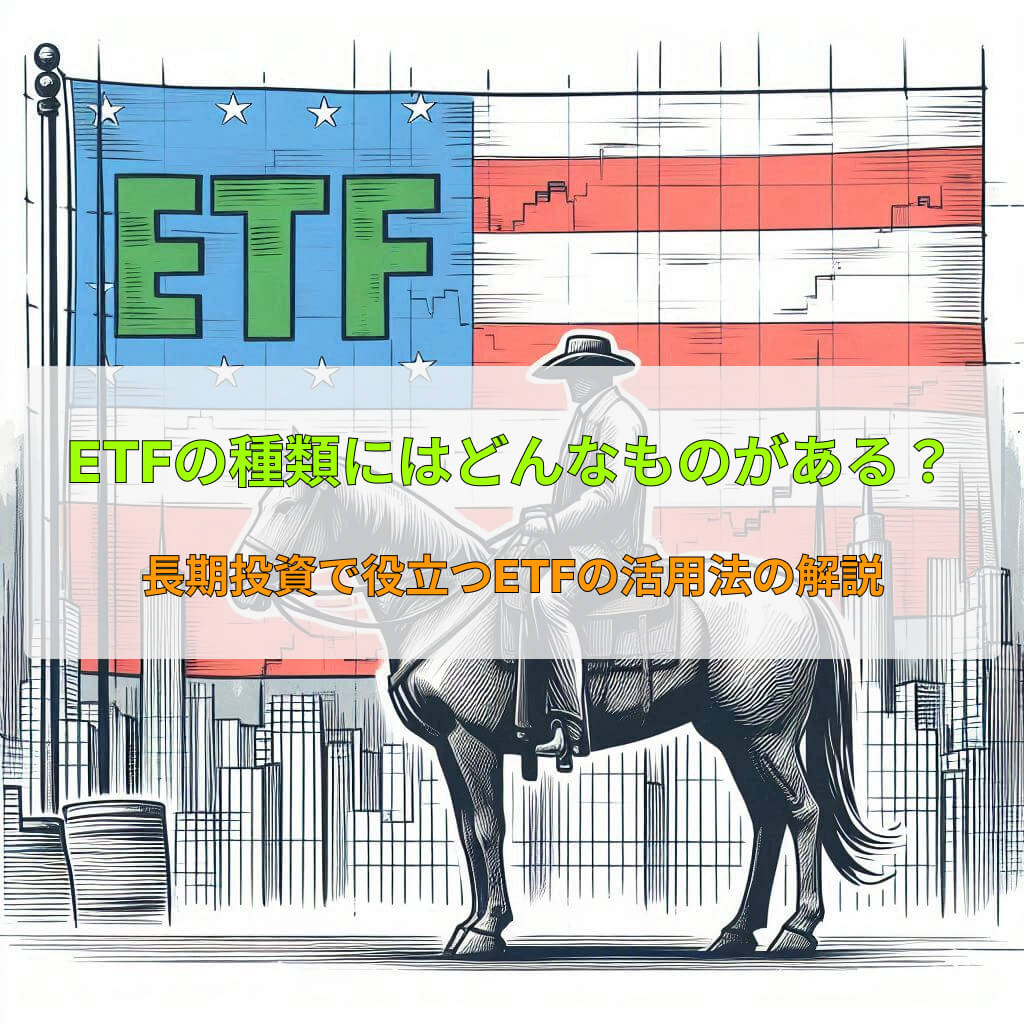『インデックスリバランスとは?』
インデックスファンドやETFへの投資では、時間の経過とともに市場の変動や銘柄構成の変化により、当初の資産配分が次第に崩れていくことがあります。
そこで重要となるのが「インデックスリバランス」です。
本記事では、インデックスリバランスの基本的な考え方から、具体的な実践方法までをわかりやすく解説していきます。
この記事で分かること
- インデックスリバランスの基本的な仕組み
- なぜリバランスが必要なのか
- リバランスの具体的な実践方法

投資戦略におけるインデックスリバランスの活用方法について、詳しく見ていきましょう。
インデックスリバランスとは?
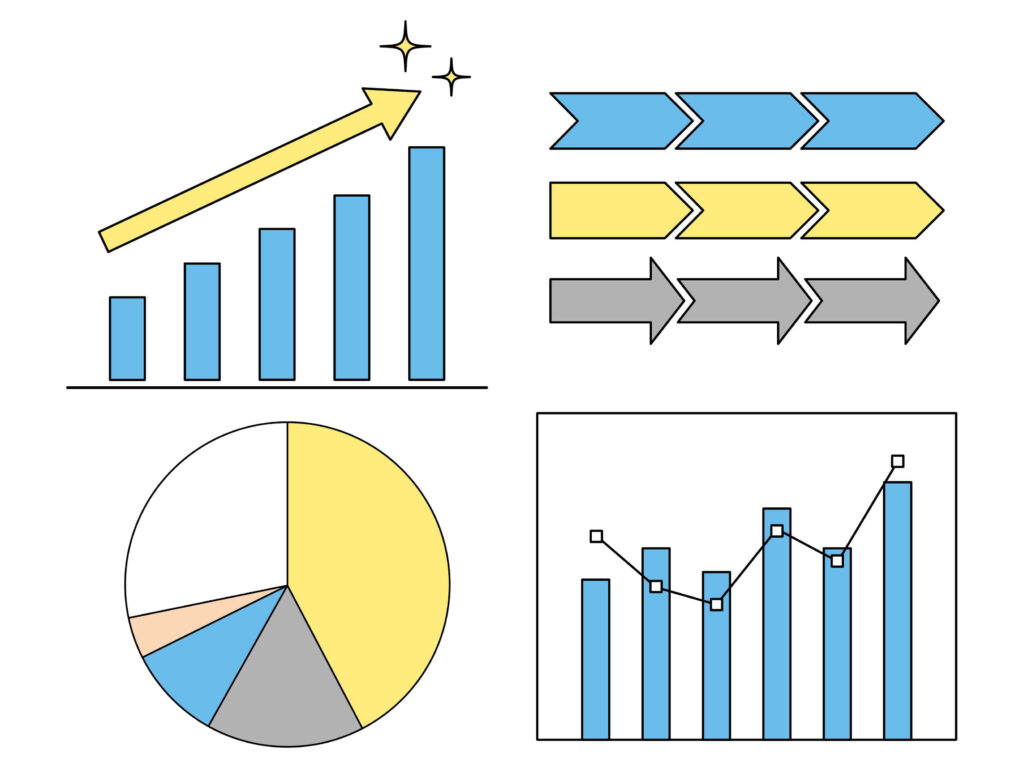
そもそも、インデックスとは市場全体の値動きに連動する代表的な指標のことです。
個別の株式や債券を保有するのとは異なり、インデックスに連動するファンドを活用することで、市場全体に効率的に分散投資できるというメリットがあります。

まずはじめに、インデックスリバランスの基本的な特徴について確認していきましょう。
インデックスリバランスの基本的な特徴
インデックスリバランスとは、インデックスファンドやETF(上場投資信託)を運用する際に、ポートフォリオの構成比率を調整する手法です。
インデックスファンドやETFは、特定の市場インデックス(たとえばS&P 500や日経225など)に連動しているため、銘柄の価格や時価総額の変動により構成比率が変わります。
そのため、各銘柄や資産クラスの比率が目標比率から大きく乖離した場合には、その比率を目標に近づけるために売買を行い、ポートフォリオの目標とする資産配分を維持します。
例えば、S&P 500に連動するインデックスファンドでは、構成企業の株価が変動すると、ファンド内の各銘柄比率も変動するため、定期的にリバランスを行い、目標の資産配分を維持します。

投資におけるポートフォリオとは、株式・債券・投資信託・不動産など、複数の資産にどのように分散して投資しているかを示すものです。
関連コラム
・ポートフォリオ戦略|資産運用を成功に導く効果的な組み方とは?
なぜインデックスリバランスが必要なのか?
インデックスリバランスが必要な理由は、主に次の3点にあります。
①リスク管理
市場の動向により、特定の銘柄が急激に成長したり、逆に低迷することがあります。
これにより、ポートフォリオ内で特定の資産が過度に偏ることがあり、リスクが集中してしまいます。
そのため、定期的にリバランスを行うことで、この偏りを是正し、リスクを適切に管理します。
➁目標資産配分の維持
投資戦略に基づいて設定した資産配分(例えば、株式と債券の比率)が、市場の変動によって変わってしまうことがあります。
リバランスによって、元々の配分比率に戻すことができ、戦略に沿った投資を維持できます。
③利益の確保
市場が上昇した際には、利益が出ている銘柄の比率が増加します。
そのため、リバランスによって利益を確定させることができ、同時に新たな投資機会に資金を振り分けることができます。

上記3つのポイントを含め、リバランスの必要性については、次章で掘り下げてご紹介します。
資産運用について相談できるサイト
・【マネードットコム】
インデックスリバランスが投資戦略に与える影響
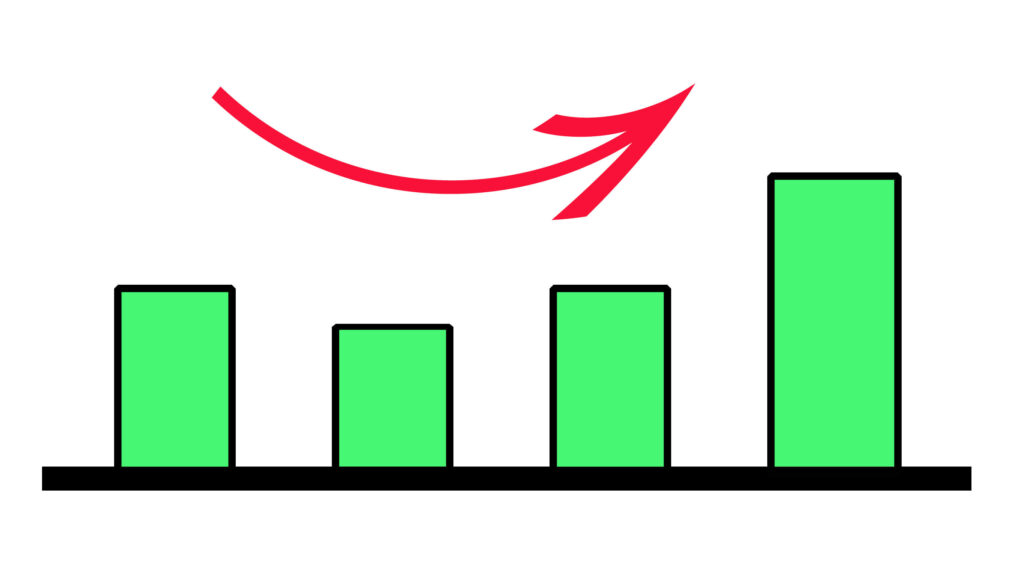
前章でご紹介したように、リバランスを行うことでリスクをコントロールしながら、資産配分を最適な状態に保つことができます。

次に、インデックスリバランスが投資戦略に与える影響について見ていきましょう。
リバランスがもたらす2つのリスク管理効果
リバランスによるリスク管理の効果には、主に次の2つのポイントが挙げられます。
1. 市場変動への対応
リバランスは、市場の急激な変動に柔軟に対応するための手段として有効です。
たとえば、株式市場が急落した場合には、リバランスによって値下がりした株式を買い増すことで、ポートフォリオ全体を割安な水準で強化し、将来の市場回復時に利益を得やすくなります。
2. 長期的なリスク管理
リバランスを定期的に行うことで、時間の経過とともに生じるリスクの偏りを是正することができます。
たとえば、成長株が過剰に上昇した場合、そのリスクを債券など安定資産に移すことで、長期的な価格変動に対する耐性が強化されます。
リバランスで期待できる3つのパフォーマンス向上効果
リバランスによって期待できるパフォーマンス向上の効果には、主に次の3つのポイントがあります。
1. 感情に左右されにくい投資判断の促進
定期的なリバランスは機械的に資産配分を調整するため、市場の急激な変動やニュースに惑わされて感情的に売買を繰り返すリスクを減らします。
これにより、冷静で一貫性のある資産運用が可能になり、長期的な成果につながりやすくなります。
2. 市場のボラティリティを活用したパフォーマンス向上
市場の価格変動を活かして、割安になった資産を積極的に買い増し、高値で評価されている資産を売却します。
このタイミングを自動的に調整できるため、価格変動の波を利用した効率的な資産運用が期待できます。
3. 税効率の改善
リバランスの際に売却タイミングをコントロールすることで、譲渡益課税の影響を抑えたり、損失を損益通算に活用したりすることが可能です。
これにより、税負担を軽減しながら効率的に利益を確定し、手取りの投資成果を最大化できます。
あわせて読みたいコラム
・レバレッジ型・インバース型投資信託の特徴とリスク管理のポイント
インデックスリバランスの実践方法
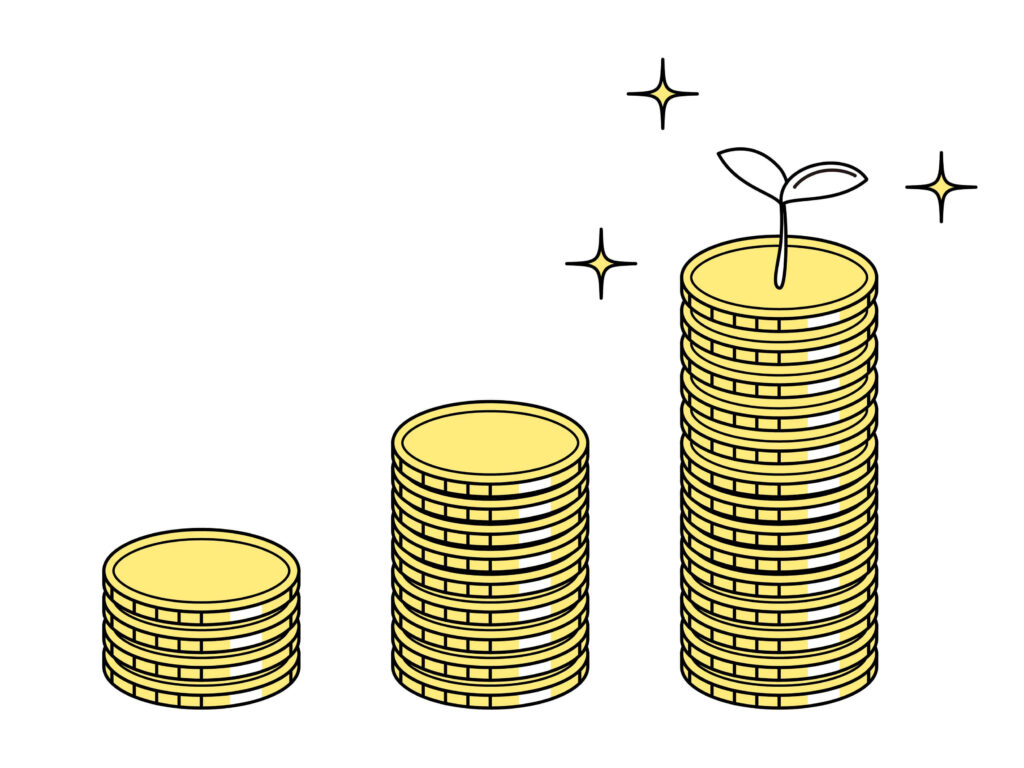
リバランスのタイミングや手法にはさまざまなアプローチがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

最後に、インデックスリバランスの具体的な実践方法について見ていきましょう。
リバランスの実行手順と注意点
インデックスリバランスの実践方法は、一般的に以下6つのステップで進められます。
1. ポートフォリオの目標とアセットアロケーションの設定
まず、自身の投資目標やリスク許容度を確認し、それに基づいたアセットアロケーション(資産配分)を設定します。
例えば、株式、債券、不動産など、どの資産クラスにどの程度投資するかを決めます。
2. 定期的なポートフォリオの評価とリバランスのタイミング設定
インデックスリバランスは、定期的に行うことで効果を最大化できます。
そして、そのリバランスのタイミングとして、主に以下の2つの方法があります。
①時間ベースのリバランス
一定期間ごと(例:四半期ごと、半年ごと、年に1回など)にポートフォリオの評価を行い、目標とするアセットアロケーションに戻す方法。
②閾値(いきち)ベースのリバランス
特定の資産クラスが設定した比率を超えた場合(例:株式比率が80%に達した場合)にリバランスを実施する方法。
3. 現在のポートフォリオの価値を評価
リバランスを実施する際は、まず現在のポートフォリオ内の各資産の価値を確認し、目標とする比率とのズレを把握します。
その上で、どの資産を売却し、どの資産を購入すべきかを判断します。
4. 売買の実行
リバランスの実行には、過剰に増加した資産(例えば、株式など)の一部を売却し、減少した資産(例えば、債券など)を購入することが含まれます。
これにより、ポートフォリオが再び目標とする資産配分に戻ります。
5. 取引コストと税金の考慮
リバランスの際には、取引手数料や税金がかかることがあります。
頻繁にリバランスを行うとコストがかさみやすいため、税金が発生しないNISA口座やiDeCo口座の利用など、コストを抑える方法を検討することも大切です。

投資の売買には手数料や税金がかかるため、NISAなどの非課税制度を理解しておくことも大切ですよ。
関連サイト
・新NISAから始める資産運用!SBI証券での口座開設ステップ解説
まとめ
今回の記事のまとめです。
インデックスリバランスは、インデックスファンドやETFの資産比率を目標に合わせて調整する手法です。
リバランスを適切に行うことで、ポートフォリオのリスクをコントロールし、安定した長期的な運用成果が期待できます。