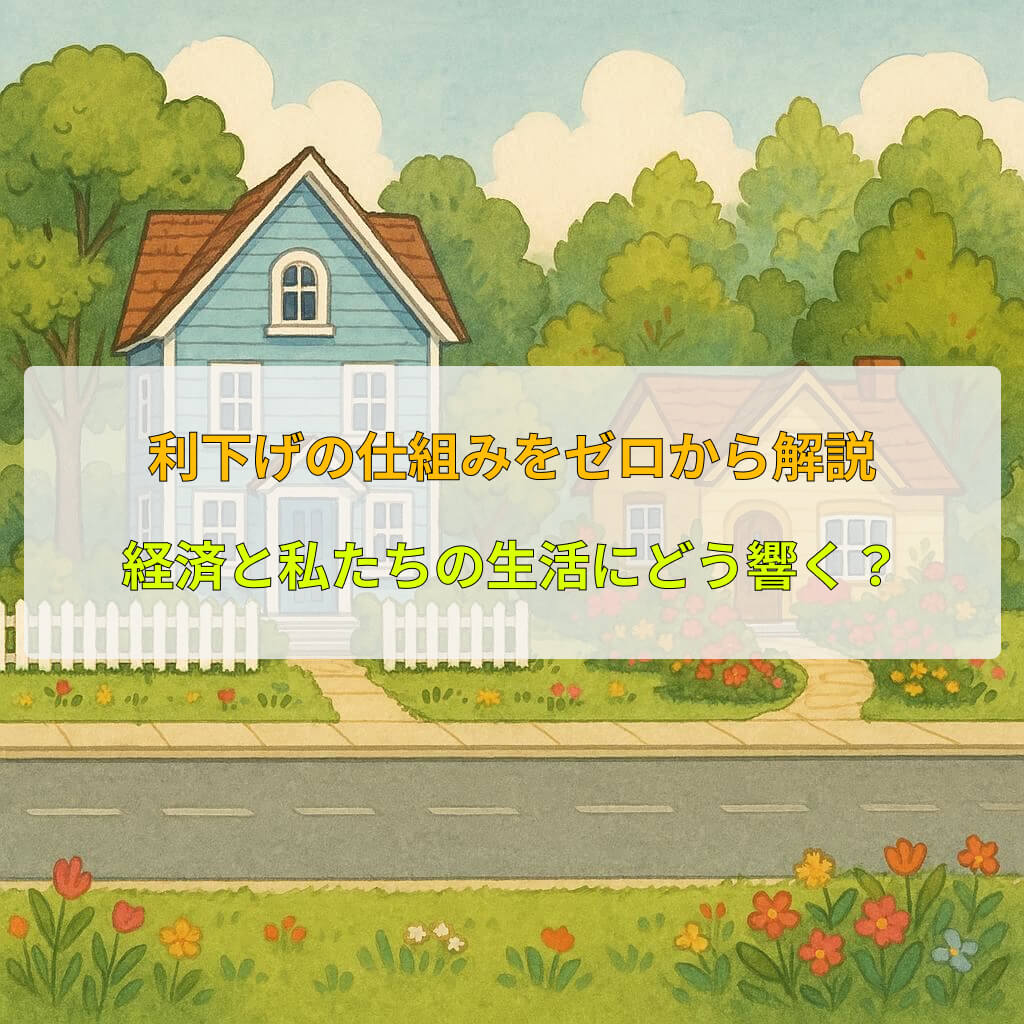金利が下がる「利下げ」。
ニュースでよく耳にする言葉ですが、実際にどのような仕組みで行われ、私たちの生活や経済にどんな影響を与えるのかは、意外とわかりにくいものです。
この記事では、利下げの基本的な仕組みから、企業や家計への影響までを、わかりやすく解説します。
この記事で分かること3つ
- 利下げの基本的な仕組み
- 利下げが経済や企業に与える影響
- 私たちの生活や家計への具体的な影響

金利の仕組みを理解して、日常生活でどのように役立てられるかを学んでいきましょう。
そもそも、金利の仕組みってどうなってるの?

一般的に、金利が上がると銀行の預金金利も上がるため、貯蓄に対する利息が増えます。
一方で、住宅ローンやカードローンなどの借入コストは高くなるため、返済負担が大きくなります。

まず最初に、金利の基本的な仕組みについて確認していきましょう。
あわせて読みたいコラム
・市場金利が住宅ローンに与える影響とは?固定・変動金利の判断基準
金利の基本的な仕組み
そもそも、金利とは、お金を借りたり預けたりする際の「利息の割合」のことです。
銀行にお金を預けると利息が付き、借りると利息を支払うことになります。
たとえば、預金に100万円を預けた場合、金利が年0.1%であれば1年間で1,000円の利息が付きます。
一方、住宅ローンやカードローンでお金を借りる場合、金利が高いと返済額も増えるため、生活や資金計画に大きな影響を与えます。
金利の主な種類
Ⓐ預金金利
銀行にお金を預けることで受け取る利息の割合。預金額や預ける期間によって利息が変わります。
Ⓑ借入金利
銀行や金融機関からお金を借りる際に支払う利息の割合。住宅ローンやカードローンなどに適用されます。
政策金利とは?
政策金利とは、中央銀行(日本なら日本銀行)が決める基準金利で、銀行同士が短期で資金を貸し借りする際に適用される金利です。
銀行にとっての「お金の仕入れコスト」ともいえ、これが変わると銀行が一般に貸し出す金利や預金金利にも影響します。

政策金利と私たちの金利の関係を整理すると、以下のようになりますよ。
政策金利がもたらす影響
Ⓐ利下げ(政策金利が下がる場合)
・銀行はお金を借りやすくなる → 企業や個人向けの貸出金利が下がる → 借入がしやすくなる
・預金金利も下がる → 貯蓄の利息は少なくなる
Ⓑ利上げ(政策金利が上がる場合)
・銀行はお金を借りにくくなる → 貸出金利が上がる → 借入の負担が増える
・預金金利は上がる → 貯蓄の利息が増える
利下げが行われる典型的な場面
では、利下げが行われる場面には、どのようなケースがあるのでしょうか。

一般的には、次の3つのシチュエーションが代表的です。
1. 景気が低迷しているとき
経済成長が鈍化し、企業の投資や個人の消費が落ち込むときに利下げが行われます。
金利を下げることで企業は借入コストを抑えて設備投資や事業拡大がしやすくなり、個人も住宅ローンや消費支出を増やしやすくなります。
2. 物価上昇率が低く、デフレ傾向のとき
物価がほとんど上がらない、あるいは下がる状況では、中央銀行は利下げで市場にお金を流し、消費や投資を促します。
これにより、経済活動が活発になり、デフレの解消につながることが期待されます。
参照サイト
・SMBC日興証券『初めてでもわかりやすい用語集 デフレ(デフレ)』
3. 国際的な経済環境が悪化しているとき
海外経済の不調や金融市場の混乱により、国内の企業や金融市場に悪影響が出そうな場合にも利下げが行われます。
金利を下げることで国内の経済活動を支え、景気の下振れリスクを抑える効果があります。
中央銀行が金利を動かす理由
中央銀行が金利を動かすのは、主に景気の調整と物価の安定を目的としています。
景気が低迷しているときは金利を下げることで、企業や個人が借入しやすくなり、消費や投資が促進されます。
逆に、景気が過熱して物価が上昇しすぎる場合は、金利を上げて借入を抑制し、経済の過熱や物価上昇を防ぎます。

上記の影響が、企業や家計にどのように表れるのか、次章以降で確認していきましょう。
住宅ローンの借り換えについて相談したい!👇
・住宅ローンの借り換えはモゲチェック
利下げのメカニズムと経済への波及
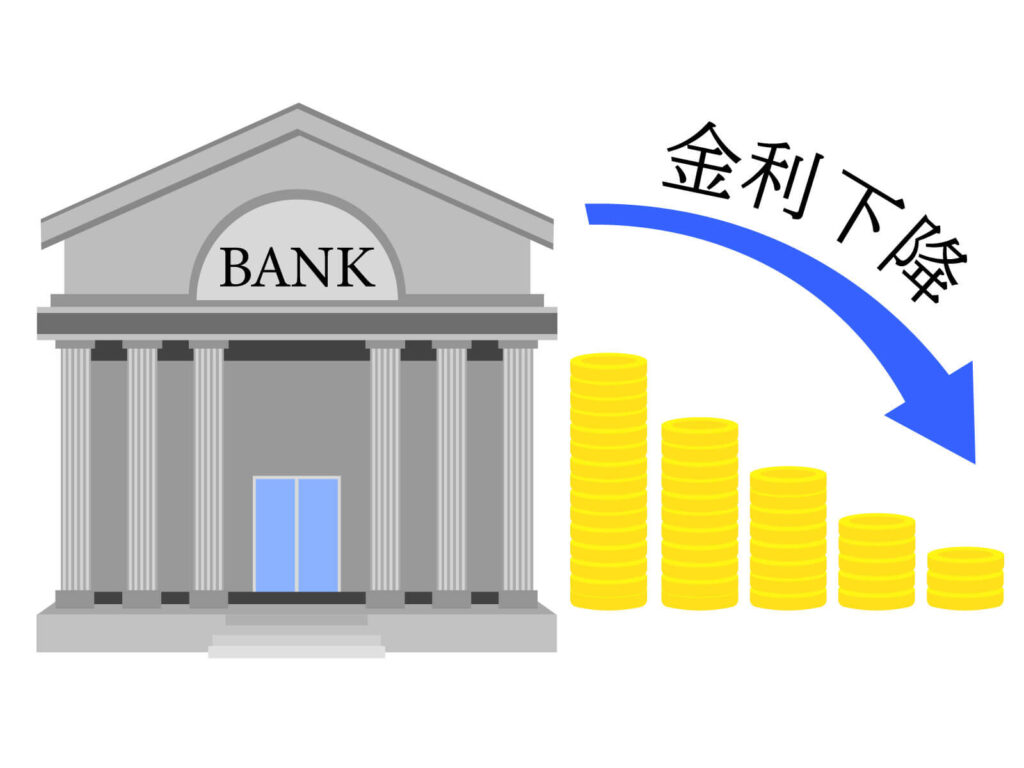
先ほどの章では、金利の基本的な仕組みについて確認しました。
では、その金利の利下げは、企業や経済活動にどのような影響を与えるのでしょうか。

この章では、利下げがもたらす企業や経済への影響について解説していきます。
企業活動・投資への影響
利下げは、企業の資金調達コストを下げ、設備投資や事業拡大を後押しします。
たとえば、年間1億円の借入を行う企業で、政策金利の引き下げにより利率が2%から1%に下がった場合、年間の利息負担は100万円減少します。
この減少分を、新しい生産ラインの導入やITシステムの更新、研究開発費に回すことで、将来の収益拡大や生産性向上につなげることができます。

資金調達コストが下がる仕組みを簡単にまとめると、次の図のようになります。
資金調達コストが下がる仕組み
1. 中央銀行が政策金利を引き下げる
↓
2. 銀行の貸出金利や社債利回りなど市場金利も低下
- 銀行融資の利率が低くなる
- 社債発行の利息も減少
↓
3. 企業の利息負担が減少
- 例:年間1億円借入の場合、
利率2%→1%で利息が200万円→100万円に減少
↓
4. 余裕資金を事業投資や設備投資に回せる
- 生産ライン導入、ITシステム更新、研究開発費など
↓
5. 企業活動の活発化・成長促進
- 設備投資や新規事業拡大を通じて将来の収益拡大や生産性向上につながる
利下げが行われることの注意点
メリットしかないように思える利下げですが、一方で注意点もあります。
借入コストが下がることで過剰投資や不採算事業への資金投入が増え、短期的な景気刺激が長期的な財務健全性を損なう可能性があります。
特に、新規事業や設備投資が慎重に計画されていない場合、期待した収益を上げられず、返済負担だけが残るリスクがあります。
さらに、長期間の低金利は金融機関の利ざやを圧迫し、貸出態度が慎重になることもあるため、資金調達のしやすさに格差が生じる場合があります。
そのため、すべての企業が低金利の恩恵を十分に享受できるわけではなく、財務計画やリスク管理の重要性が一層高まります。

利下げは為替相場にも影響を及ぼすことがあるため、以下2つのポイントもチェックしておきましょう。
①円安が進む可能性
金利低下により円安が進むと、輸出企業には利益拡大のチャンスとなりますが、輸入品や海外資材のコスト増で国内企業には負担となる場合があります。
②円高に振れるリスク
円高が進むと輸入コストは抑えられますが、輸出企業の売上や利益が減少し、企業の投資計画や収益に影響を与える場合があります。
あわせて読みたいコラム
・結局、円安・円高って何?海外旅行で損しないタイミングをやさしく解説
利下げが私たちの生活に与える変化
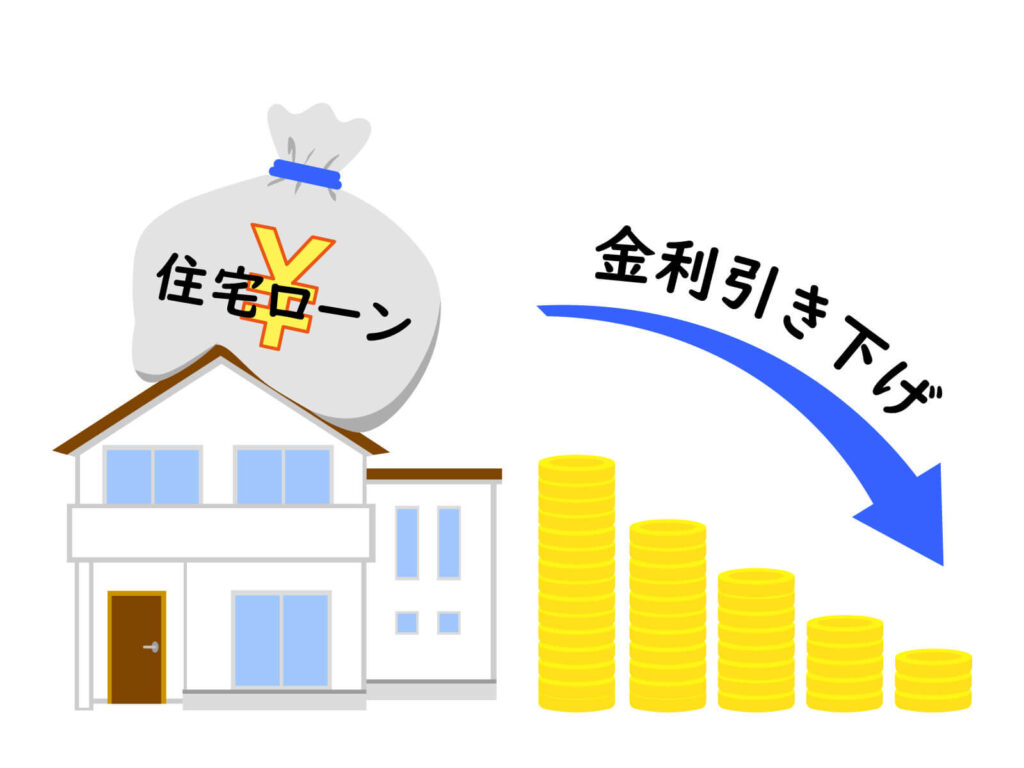
先ほどの章でお伝えした通り、利下げによって企業の資金調達コストは下がり、投資活動や事業拡大がしやすくなります。
では、私たち一般家庭にとっては、どのような影響があるのでしょうか。

最後に、利下げが一般家庭に与える影響と、その対策について見ていきましょう。
ローン・借入に有利な環境の活用
利下げは、住宅ローンや自動車ローンなどの借入金利を下げる効果があります。
そのため、住宅ローンなどの長期借り入れでは毎月の返済負担が軽くなり、家計に余裕が生まれやすくなります。
たとえば、借入残高が3,000万円で金利が2%から1%に下がった場合、年間の利息負担は約30万円軽減され、その分を生活費や教育費、貯蓄に回すことが可能になります。
関連コラム
・固定金利は3年・5年・10年どれが得?住宅ローンの選び方ガイド
積立型保険は同じ保険料でも差が出る
学資保険や個人年金保険などの積立型保険は、契約時に設定される「予定利率」をもとに、将来の受取額が決まります。
予定利率が高ければ、同じ保険料でも受け取れる金額は大きくなります。
しかし、利下げによって市場金利が低下すると、保険会社は運用で十分な利益を上げにくくなり、契約時の予定利率や市場の金利状況によって、受取額に差が生じることがあります。
そのため、積立型保険に加入する際は、予定利率の水準や利下げの影響を適切に理解したうえで判断することが大切です。

積立保険で将来どのくらい受け取れるのか気になる方は、FPに相談してみるのがおすすめですよ。
関連コラム
・FPに相談するメリットとは?お金と保険の専門家だからできること
貯蓄・預金金利の低下と資産運用の選択肢
お伝えしてきたように、利下げは、一般家庭にとって住宅ローンなどの借入金利を下げる効果があります。
一方で、預金利息は減少するため、預金だけで資産を増やすことは難しくなります。
そのため、株式や投資信託、債券、税制優遇制度を活用した資産運用への関心が高まる傾向にあります。

預金に代わる主な資産運用には、以下のようなものがありますよ!
・株式
価格変動リスクはあるものの、長期的に高いリターンを期待できる。
・投資信託
少額から分散投資が可能で、リスクを抑えながら運用できる。
・債券・個人向け国債
比較的安定した利息収入を得られる。
・iDeCo・NISA
税制優遇を受けながら効率的に資産形成が可能。
FPに無料相談できるサイト
・【マネードットコム】
まとめ
今回の記事のまとめです。
利下げとは、中央銀行が政策金利を下げることです。
これにより企業は資金を借りやすくなり、住宅ローンなど私たちの借入金利も下がるメリットがあります。
一方で、預金だけで資産を増やすことは難しくなるため、利下げの影響を理解しておくことが大切です。