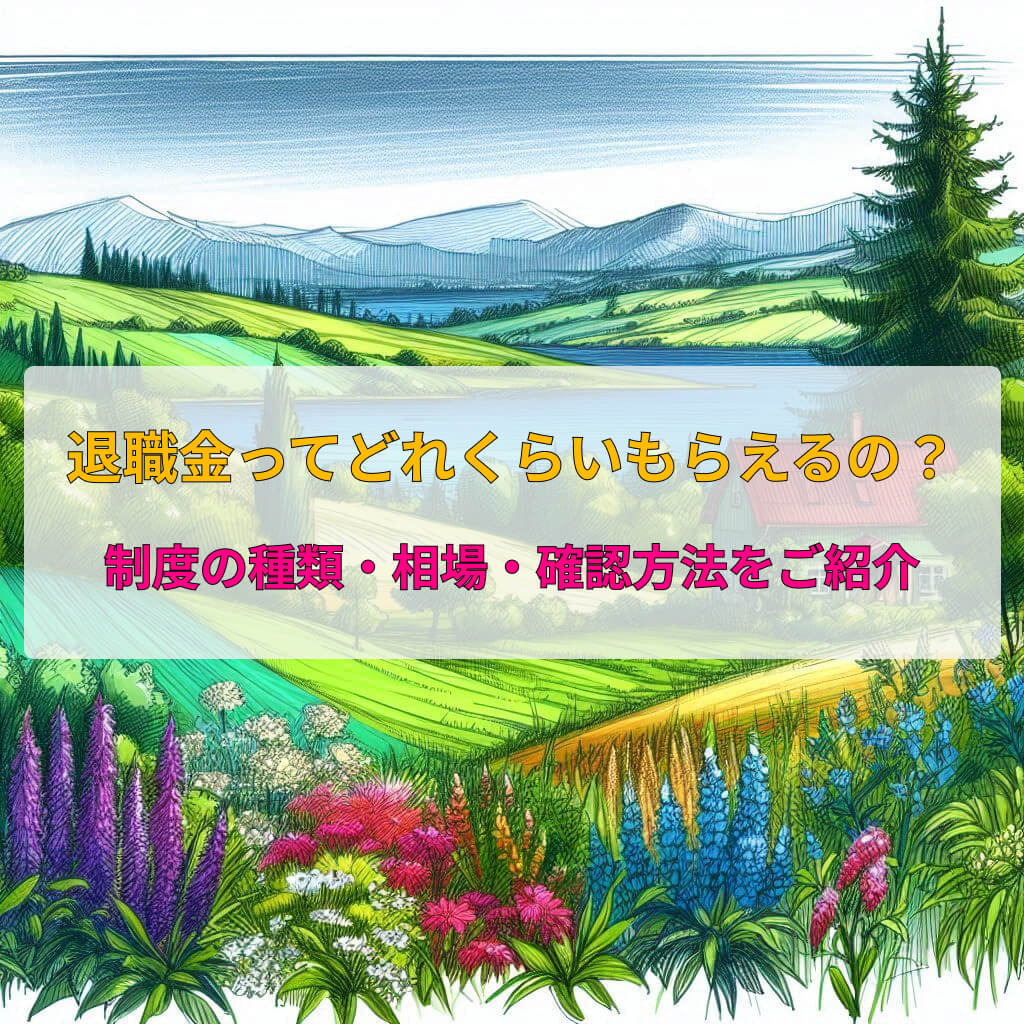『退職金の受け取り方の違いって?』
退職金を受け取る際、多くの人が悩むのがその受け取り方法ではないでしょうか。
その主な選択肢として『一括受け取り』と『年金での分割受け取り』の2つがありますが、
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自身にとってどちらが最適かを判断しなくてはなりません。
本記事では、一括受け取りの特徴を詳しく解説し、年金による分割受け取りとの違いについてご紹介します。
この記事で分かること
- 退職金の一括受け取りの仕組みと特徴
- 年金として分割受け取りする方法との違い
- 自身に合った退職金の受け取り方の考え方

退職金の一括受け取りが老後のライフプランに与える影響について、一緒に考えてみましょう。
退職金の一括受け取りとは?
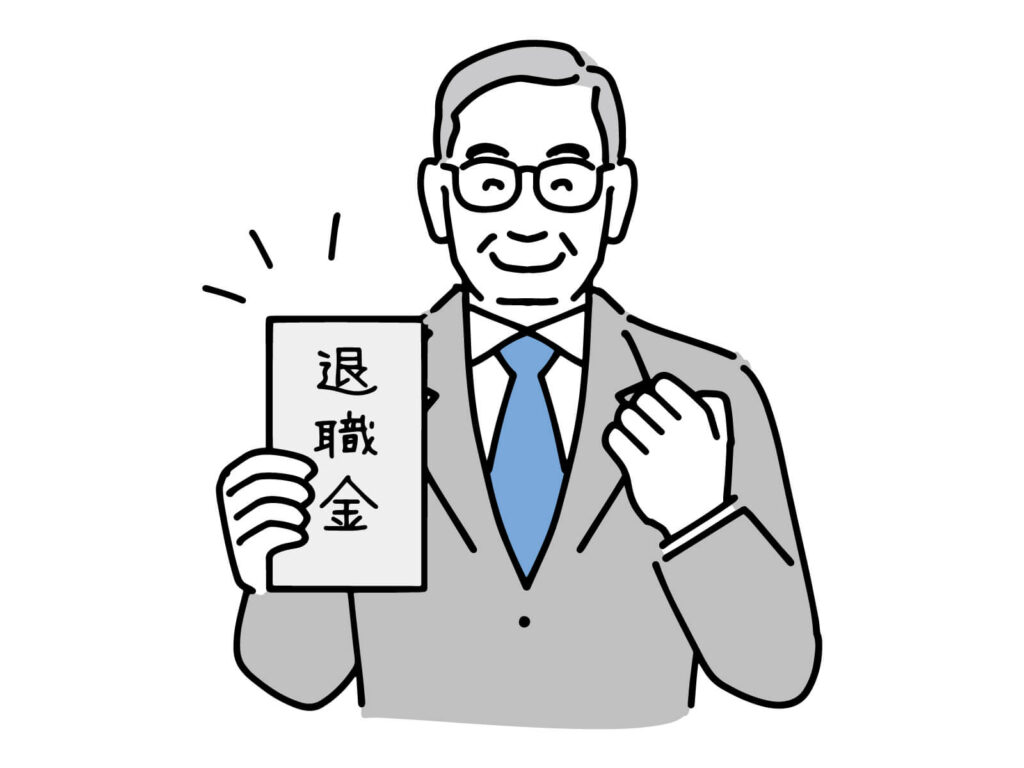
退職金の受け取り方法としては、一括で受け取ることを思い浮かべる方が多いかもしれません。
一度にまとまった資金を手にできる点は大きなメリットですが、その年の所得として扱われるため、課税額が増える可能性がある点には注意が必要です。

初めに、一括受け取りにはどのような特徴があるのかを確認していきましょう。
そもそも、退職金の受け取り方法の違いとは?
そもそも、退職金の受け取り方法には主に3つの選択肢があり、それぞれで税金の取り扱いが異なります。

退職金の3つの受け取り方法は、以下の通りです。
①一括での受け取り
退職金を一括で受け取る方法で、退職所得控除が適用されます。
➁分割での受け取り
退職金を数回に分けて受け取る方法で、公的年金控除が適用されます。
③その両方の組み合わせ
一部は一括で受け取り、残りは分割で受け取る方法で、それぞれの控除が適用されます。
退職金を一括で受け取るメリットとデメリット
退職金を一括で受け取る方法には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
①税金負担を軽減できる
退職所得控除が適用されることで、税負担が軽減され、結果として手取り額が増加します。
➁柔軟な生活設計ができる
一度にまとまった金額を得ることで、老後の生活設計や事業資金の確保など、自由に使える資金を手に入れることが可能になります。
デメリット
①超過分に税金がかかる
退職金が退職所得控除を超えると、超過分に税金が課され、その結果、手取り額が減少する可能性があります。
➁生活資金が不足するリスクがある
一括で受け取った退職金を計画的に活用しないと、後々の生活資金が不足するリスクが高まります。

退職金を受け取る前には、今後のライフプランを明確にしておくことが大切ですよ!
参照コラム
・ライフプラン表ってどんなもの?結婚・出産・退職を可視化するメリット
2つの受け取り方法の違いと特徴
お伝えしてきた通り、退職金を受け取る際は、一括で受け取るか、年金形式で分割して受け取るかのいずれかを選ぶのが一般的です。

以下の図1で、一括受け取りと分割受け取り、それぞれの特徴の違いを確認してみましょう。
| 一括受け取り | 年金での分割受け取り | |
|---|---|---|
| 税金の控除 | 退職所得控除が適用され、一定額まで非課税 | 公的年金等控除が適用され、毎年の所得税が軽減 |
| 税金負担 | 高額の場合、控除を超えた部分に税金がかかる | 毎年の収入として扱われるため、税負担が分散される |
| 受け取りの柔軟性 | まとまった資金を自由に使える | 定期的に一定額を受け取るため計画的な利用が可能 |
| 資金管理のリスク | 資金を一度に使い切ってしまうリスクがある | 長期的な資金管理がしやすく、生活費の安定に寄与 |
| 受け取りのタイミング | 退職後、数ヶ月以内に一度に振り込まれる | 毎年または毎月、決まった金額が振り込まれる |
| 老後の生活設計 | 住宅ローンの返済や事業資金など大きな支出に対応可能 | 老後の生活費として計画的に利用しやすい |
| 手続きの手間 | 一度の手続きで完了 | 定期的な受給手続きが必要 |
一括受け取りの手続き方法
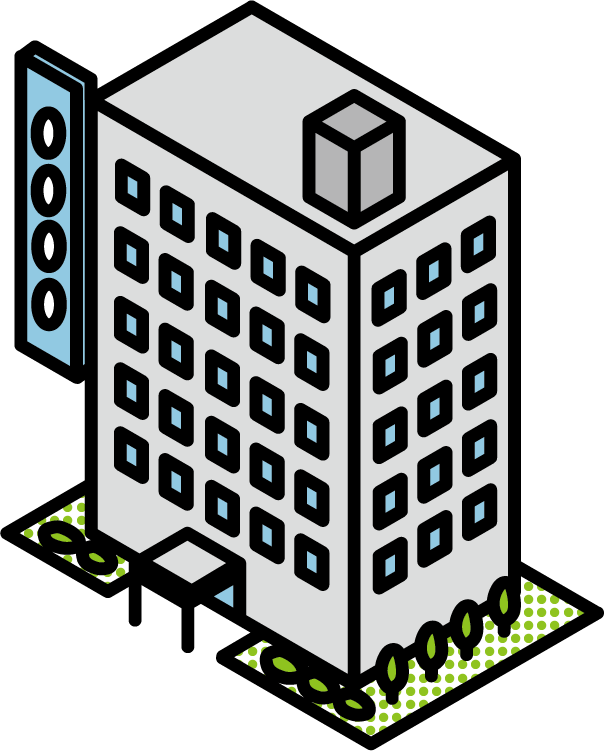
退職金を申請する際には、特定の書類を提出する必要があります。
次に、この章では、一括受け取りの手続き方法について見ていきましょう。

なお、多くの企業では、一般的な退職金制度として中退共制度が活用されています。
あわせて読みたいコラム
・中退共制度の掛け金いくら?経営者・従業員が知っておきたいポイント
必要書類等の入手
退職金を一括で受け取るためには、いくつかの必要書類が求められます。

退職金請求時に必要な書類は、主に以下の3つです。
①マイナンバー入り住民票(コピー不可)
②身元確認書類のコピー
③退職金(解約手当金)請求書
参照サイト
中小企業退職金共済事業本部『7.退職手続きについて』
一括受け取り時に注意すべき2つのポイント
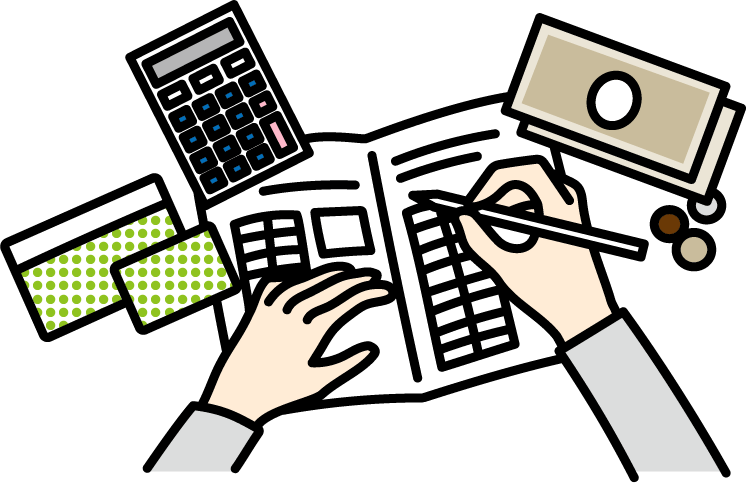
一括受け取りのメリットは、退職金をすぐに現金として受け取れる点にあります。
しかし、退職金を一括で受け取る際には、いくつかの注意点も存在します。
最後に、一括受け取り時に注意すべき2つのポイントについて解説します。

退職金を受け取った後のライフプランに、どのような影響があるのかを考えてみましょう。
1. 退職金にかかる税金を理解する
退職金には「退職所得」という特別な課税方式が適用されます。
そのため、一括で受け取る場合は、まずこの退職所得がどのくらいになるのかを確認しておく必要があります。

退職所得金額の求め方は、以下の通りです。
退職所得金額 = (退職金 - 退職所得控除) × 1/2

退職所得控除については、以下の計算式または参照コラムをご覧ください。
退職所得控除の計算式
退職所得控除額は、勤続年数によって異なります。
Ⓐ勤続年数20年以下の場合
退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数
Ⓑ勤続年数20年以上の場合
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
参照コラム
・退職金所得控除の求め方|早期退職と定年退職の税金の違い
2. 老後資金のプランを見直す
退職後の生活を安定させるためには、老後資金のプランを見直しておくことも大切です。

以下の、ⒶⒷ2つの要素を確認してみましょう。
Ⓐ老後に必要な資金の再評価
老後に必要な資金には、主に以下2つの支出が含まれます。
①生活資金の見直し
住宅ローンの完済や子どもの独立による支出の変化、医療・介護費用の増加などを踏まえ、老後資金を見直すことが大切です。
➁医療・介護費用の備え
退職後の健康管理や介護に備えるため、医療保険や介護保険への加入や見直しも有効です。
Ⓑ年金受給開始時期と私的年金の関係
年金は自身のタイミングで受け取れますが、受給開始時期や私的年金との関係も確認しておきましょう。

老後のライフプランの有効化には、以下のコラムをご参照ください。
あわせて読みたいコラム
・老後資産2,000万円どう準備する?資産形成対策が必要な理由とは
まとめ
今回の記事のまとめです。
退職金の受け取り方法には、一括受け取り、分割受け取り、またはその両方を組み合わせる方法があります。
一括で受け取る場合、退職所得控除を活用して税負担を軽減できるメリットがありますが、控除額を超えると一度に大きな税金がかかり、手取り額が減るリスクもあります。
そのため、一括受け取りを選ぶ際には、税金の影響を理解し、老後資金の計画を見直すことが大切です。